私の住む東大阪に隣接する平野が、かつて自治都市であったことを最近テレビニュースで知った。堺が自治都市であったことは有名だが、自分の住んでいる近くの町がかつて自治都市であったことは知らなかったので、とても驚いた。自治都市とは、時の権力のに対峙し、その影響を被らない独自の権力をもつ都市のことである。ニュースでは、その自治都市の名残が存在することを解説していた。杭全神社の大門が重要文化財に指定されていないことがそれである。重要文化財に指定することは、国からお墨付きを得ることである。観光客の増加、修繕・維持費用の肩代わりなどが見込める代わりに、その文化財の扱い方などは国の指針に従わざるを得ず、つまり所有権の一部を譲渡することを意味するのである。杭全神社の大門は、鎌倉時代に造られたもので、非常に歴史的価値が高いにも関わらず、重要文化財になっていない。その理由は、だんじり祭りのさいに、大門を山車が通れないため、石垣で嵩上げされているためである。明治時代に山車の倉庫が境内の外部に移動したため、当時の住民は、国宝指定の通知が来ていたにもかかわらず「神様にだんじりを見てもらう」方を優先し、嵩上げを行ったのである。つまり、国からのお墨付きを捨て、祭りへの誇りを選んだのである。
誇りとは、世間が自分たちをどう見ているかによって生じる場合、一瞬で燃え上がるがすぐに消えてしまう。「美しい国」である日本を、外国人や政治的に対立す者ににアピールしたり、ネットに溢れる日本の技術や優れた日本人に対する称賛動画などは、一瞬の高揚をもたらすが、誇りという権力として体内に息づくことはないのだ。これは、誰に対して誇るかということと、誇る対象との交錯という問題が根底にある。誇る相手が誇る対象の中に入り込んでいる場合があるのだ。この点に関しては、また別の機会に考察したいと思う。
平野の自治への誇りを知って私は嬉しかった。しかし同時に思うことがあった。所詮私も、自治を保とうとする権力とそれに伴う暴力や規律の外にある部外者であるから、それを誇りを喜ぶのであり、その内部にいたらきっと耐えられず、町を捨てて、外に逃げ出すだろうということである。そこには、父の権威が宿り、伝統を守り、年配を敬い、そして暴力が伴うからだ。
では、この自治の外、つまり父の権威の外部では、何が人と人との間を繋ぐのだろうか?それは、商品であるという答えは簡単かつ正しいものであるが、ここではひとまず保留しておく。私は、人と人とを繋ぐもののうちに安らぎたいのである。現代においては、父の権威の外部を定義することは難しい。なぜならば、父の権威が宿る場所がほとんど見受けられないため、その外部を定義できなくなってきているからである。つまり、すべてがその外部だともいえる。町、会社、学校、寮、家どこにも自治は存在しない。
自治が消滅し、それに伴って暴力も消滅したのか?パワーハラスメント、カスタマーハラスメントと呼ばれるものが、その代わりとして生まれるようになった。これらは、父の権威を根拠とした暴力ではないことは明らかだ。では、パワハラが生じる人間関係とはどういうものなのか?私は、それを考察する前に、父の権威に伴う暴力とパワハラやカスハラを同一の「暴力」というくくりで考察するのを止めたい。そして、昔と今のどちらが良いということではなく、第三の可能性を模索したいのである。
「ゆとり世代」の人と呼ばれる私は、父の権威の宿るところ、私の場合は大学の部活動であったが、それに馴染めなかった。部活内にひどい暴力が存在したわけではない。しかし、上下関係が怖かった。先輩の言動の中には、またその先輩やOBの言動が宿る。言動の主体は誰なのかという困惑が、自分は誰なのかという自己の存在の不確かさを生んだ。それがとても嫌だった。従いながらも、とても耐えられないことを所々で表現することで、伝統を壊していったように感じる。部活動においてはその破壊の第一波のように自分たちを見ている。いくつか下の後輩は、上下関係の崩れたところで、仲良くやっていた気がする。しかし、耐えられないものではあったが、部に長らく息づく良い伝統を壊していると感じていた自分は、それが崩れたフラットな関係のなかにも安らぎを得られず、一生続くような人間関係を誰とも結べなかった。
その後悔は、十数年たった今へと続く。これは帰属と依存の問題である。この二つは切り離せないものである。国家への依存、大企業への依存を軽減することが、誇りを取り戻す第一段階だと思っている。しかし、それが安らげる人間関係への帰属にいかに結びつくかは、この考察ではまだ到達できない。目標は考察することではなく、現実に安らぐことである。そのための第一歩を踏み出さないといけない。
まず、父の権威が喪失したところに、パワハラと呼ばれる新種の暴力が生じたのであるが、これは非暴力から生じた暴力なのである。これが生じる人間関係には、すでに第三者が入り込んでいる。一方の側は、もう一方に「~しろ」と命令できない。命令を正当化する根拠が命令する側に存在しないがために、非暴力的な形態をとる。それが、「〇〇が怒るから、~するのを止めてください」「~しなければ、〇〇が悲しみますよ」といった類のものである。第三者とは、家庭においては、近親者が当て嵌まり、会社においては「お客様」がそれに該当する。両者に当てはまるのが、「世間」である。世間は、家庭にも会社にも流入しているのである。
かつて、暴力を振るう主体は、伝統へと自己を同一化し、その正当性を得ていた。今、パワハラをという暴力を行う主体は、世間やお客様に媚びる(=依存)することによって、部下に対してパワハラを振る正当性を得ている。つまり、正当性の根拠が内部から外部へと移行したのである。内部にある場合、それが誇りとなりえるのであるが、外部にある場合は不可能であろう。これが自治が存在しうるかどうかの差異である。現今の会社は、内部の規律を保つために、世間やお客様を内部に流入させ続け、独自の規律や誇りを捨て去っていった。カスハラは、パワハラを上司が行うために利用される場合もある。いや、明らかには利用されずとも、お客様の過剰な要求に、対応し続けることを厭わないこと自体が、内部の規律を正常化させることに役立っているのである。カスハラとは、その意味で会社に必要な潤滑油なのである。カスハラの場合においては、お客様と店員の間に、企業という第三者が入り込んでいる。店員は企業の一部ではなく、むしろ依存しているお客様のほうが、企業のトップ、トップというものがどこであるかは不確かではあるが、そこへ近いのである。「店長を呼べ」と怒鳴る客は、トップに怒りをもつと同じだけ、トップに親しみを抱いて抱いており、不手際をした店員を一緒に罰してほしいいと思っているのである。店長の欲望を自分の欲望と同一化しているわけである。欲望とは他者の欲望であるというラカンの言葉は有名である。カスハラがなくならないのは、それが企業にうまく利用されているのだから仕方がない。また、世間の目がパワハラの問題に向けられても、パワハラを産み出しているのもまた、この世間の目の会社への流入なのだから、これもまた無くならない。
これらの新しい暴力が、国民でありかつ消費者である私たちの、国家や大企業への依存によって生じているのは明らかである。それが、会社や学校、家庭の中にまで逆流し、人間関係のよりどころを不確かでありながら、均一な無機質なものへとしている。家族や同僚や生徒同士の間に、独自の人間関係のよりどころをいかに再発見すればよいのだろうか?
この問題は、日本に急増している外国人においてはなおさらだ。しかし、このよりどころの無さが利用されているのだ。このよりどころの無さは、外国人に腹を立てても、直接行動を起こせない要因となっている。まったく人間関係のよりどころ(=文化)を持っていない場合、矯正不可能な者として現前するのである。すると人は、矯正不可能なものに対して暴力を振るえないのだ。根絶という恐ろしい暴力への意志を生むことにもなるのだが、それは個人の為しうることではないがために、直接の暴力としては生じない。この暴力の振るえなさが、国家や大企業に利用される。コンビの店員などが外国人に代わっていくのがそれである。そして、暴力を振るえない、矯正不可能な者を罰するためには国家や大企業にお願いし、それを代行してもらうしかないのである。これが国家や大企業への依存を生む。分裂の種を撒かれながら、撒いたものに依存するというのが現代の私たちのあり方である。それでは誇りは生まれようがない。
父の権威の喪失とともに、現実の父への嫌悪と恐怖が生じるのかもしれない。私の父は、世間という第三者を家庭に流入させただろうか?いや、していない。私は父を世間から浮いた存在と見ることによって、その嫌悪を正当化していたのかもしれない。家庭内に世間を導きいれたのは、子である私のほうであった。それによって父から自分を守ろうとしていたのである。自分の実体験からもわかるように、世間は、親から子、教師から生徒、上司から部下という一方通行路で流入するのではないのだ。私の父は世間からも家庭からも浮いてたのであろうか?いや、それは私の見方の問題なのだろうか?いや、父が意志的に世間からも家庭からも浮いていたのかもしれない。父の権威の喪失のなかで、誇りを失わないための格闘が父の中であったのかもしれない。


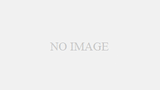
コメント