「法医学鑑定によって保証される医学的なものと司法的なものの接合は、道徳性の初歩的なカテゴリーと呼べるようなものを再活性化することによって、すなわち、倒錯性という概念を中心に配置される「傲慢」、「頑固」、「悪意」などのカテゴリーを再活性化することによって、初めて実現されます。つまり、医学的なものと司法的なものの接合は、親から子へと向けられて子供の道徳教化を目指すような、親による本質的に幼稚で子供向けの言説の再活性化を含意し、それによって初めて実現される、ということです。」
精神鑑定書は、親が子供を叱るときに使うような言葉や、児童書に記されているような道徳教化の言葉を用い、病気と犯罪を繋ぐ異常性という領域をつくりだした。この異常性という領域は、病気と犯罪という、異なる性質をもち、それゆえ異なる専門的な言説によってしか語りうることのできなかった二つの領域を、司法の場で結びつけることを可能にした。それによって、「病気≠犯罪」という従来の刑罰免除の法則に代わって、「病気 犯罪」の余白を処罰可能な領域とするようになったのである。この余白こそが異常性という領域であり、病気に近いけれども、道徳的欠陥であるがゆえに病気とは呼べないものの領域である。それはまた「病院か監獄か」という二者択一に亀裂を入れ、治療や矯正と極刑にあたる死刑までをもが等質の場で扱えるようになったことを意味した。もはや精神鑑定書の言説は、それまで培われてきた医学的な知を、医学的=真理の言説によって、司法制度の中で機能させることを仕事としなくなったのである。つまり、精神鑑定は、妄想や狂気についての精神医学的な知を、違法行為の瞬間の精神状況の分析に用いることによって、刑事責任能力の有無を解明することを行わない。自ら医学的な権威をはく奪するようにして、日常的で幼稚な道徳的用語を用いる精神鑑定書が語るのは、犯罪者の幼少期からの非行や不道徳なふるまいなどである。これは精神医学的な知の活用の大幅な劣化を意味する。しかし、フーコーがグロテスクと呼ぶ(フーコーは侮蔑的意味でグロテスクという概念を用いていない)この劣化、権威の喪失は、それゆえに司法の場での精神医学の権力を増大することになったのである。現代ポピュリズムの代表であるトランプのSNSでの発言や安倍元首相の国会答弁に見られる現象と同様に、論戦の場を陳腐な劇場にし、自ら道化役を演じる権力の技術がここに見て取れる。
精神鑑定は幼少期から犯罪をなすまでの一人の人間の連続性を打ち立て、犯罪者であると同時に異常者を法廷へと連れ出すのである。こうして、司法の場で裁かれる対象は、なされた違法行為つまり違法行為の瞬間から、違法行為をなした存在の異常性さらには異常な存在が予告する将来の違法行為へと、位置がずらされていった。存在の異常性さらには異常な存在が予告する将来の違法行為とは、一言で言うならば危険である。つまり、危険が処罰対象に加わったのである。危険をめぐるこうした精神鑑定の諸実践は、司法の場にとどまらず、広く社会全体に広がっていった。
司法権力の中では「子供」と「死刑」は同時に成り立たない。しかし親が子を叱る言表の中では、「そんなことをしていたら将来死刑になるぞ」といった言葉で積極的に見られるようになった。親はもはやその家父長的権威によって「~しろ」とは子に言わない。親は自らの権威を捨て去って、それとは異なる審級つまり司法権力や社会常識の言説を用いるようになった。また、「そんなことしていたら○○が悲しむぞ」といったような言葉で、子を大事にしてくれている人々の失望に頼ることによって、子の非行にではなく良心に働きかけるようになっていった。こうして、家父長的権威は、子供の非行を家の中で裁くことをやめ、ときには死刑という究極の処罰にまで子の非行を結びつけることで自らの権威を失った。なぜならば本来権威とは、反発=対抗行為の可能性を否定しないものである。子が親に反発できる可能性を常に持っているにもかかわらず、それでも子が自らの意志で反発=対抗措置を諦めたときに親の権威は存在するのである。しかしながら、親が警察や裁判所といった物理的暴力装置を要請したとすると、もしくはそこまで極端でなくとも、子を道徳教化する言葉の中に物理的暴力装置の存在をちらつかせるなどしたならば、子の親に対する反発の可能性は失われる。権威に対する見せかけの反発は強まるかもしれない。しかし、それはもはや親と子の二者間の能動的な働きかけによる行為ではなくなっている。また子の良心に罪の意識を芽生えさせる場合も同様に反発の可能性を奪うため権威は失われるのである。こうした司法的諸実践の社会全体への波及は、家というものがもつ社会との無縁性を喪失させた。家は、家庭となり、社会へと良い子を供給する一装置となって駆動していくのである。現代の各家庭の道徳教化は、子を物理的暴力装置に引き渡すか、子の良心に罪の意識を芽生えさせるか、という二つの方向軸の交差する平面に位置づけられるだろう。この平面の外に新たな家の形は想像しえないのだろうか?
「殺すぞ」と言って実際に殴りかかる代わりに、冷たく「死ねばいいのに」「死ね」といった子供の言葉が見受けられるのは、大人になって社会に殺されればよい、もしくは社会から異常とみなされ、自死を選べばよいという観念を背景にしている。「殺すぞ」といって実際に誰かを殺した場合、第三者によって処刑されることが子供の身体にまで浸透しているならば、殺したい相手は二人の間の決闘によって生死を分ける敵とはなり得ない。そうではなく、そうした相手は、社会によって殺される敵、犯罪をなしうる危険な異常者として各人が作り上げなければならなくなるだろう。自らが憎む相手、もっと身近な例で言えば協調性の欠如、会社内での報告を怠る人物さえも、社会の敵と見なされうるのである。二人の間の闘争には、常に社会という名の第三者が入り込んでおり、ある一方の味方に付く。もしくは両者が社会を味方につける。これが社会の分断である。分断の中で調停をし、和解を産むのも分断を産んだ権力なのである。ルソーは、権力が和解のときにでも分断の種を蒔くと言っている。まさにその通りである。精神鑑定は、犯罪を子供の非行や不道徳を結びつけ、犯罪者であると同時に非行者である者を司法過程に出現させるにとどまらず、非行や不道徳が将来の犯罪者を産むという言説を社会一般にまで流布させることに一役買ったのである。
「医学的なものと司法的なものの接合は、親から子へと向けられて子供の道徳時教化を目指すような、親による本質的に幼稚で子供向けの言説の再活性化を含意し、それによって初めて実現される」
このように、親が子の非行を咎め、父親の権威から発する言葉ではなく精神鑑定から借り受けた言葉を用いるならば、非行少年がその親の顔に透けて見るのは間違いなく社会であろう。子供が生身の親を否定して社会へと渡り出るのが正しい成長だと一概には言えない。しかし、そうした成長は困難になるだろう。生身の親を拒絶して社会へと渡りゆく代わりに、社会の一装置としての親を拒絶してその先へ進もうとするならば、それは社会をも否定することになってしまう。その先に待っているのは、親と離れたところにある社会ではなく、親と連続性を保ったままの社会であろう。そこには矯正施設のような場所もあり、そうした場所への監禁の請求を親がなすようなことも当然出てくる。なぜならば親は子を道徳教化する際に、精神鑑定がつくりだした非行と将来の犯罪の時間的な連続性ならびに非行と病気の同時性を念頭に、監獄的な病院の存在をちらつかせるのだから、そうした審級へと子を引き渡すことも可能性として常にありうるのである。親の子に対する製造責任という言葉を最近耳にしたが、それもこのような実践から生まれたものである。少年裁判所へと送られる子供たちは、
「予審は、個人が犯した行為、つまりそれによって個人が裁判所に引き渡されることになった行為そのものに対してよりも、その個人の存在様式や生活や規律などの背景に対して、はるかに大きなかかわりを持ちます。個人が送られるのは、倒錯性と危険の法廷であり、犯罪の法廷ではないということです。」
こうした家父長的権威を無用化し、家庭へと侵入してくる司法=医学的権威は、子を異常から正常へと向かわせることによって、社会を危険から守ろうとする。司法=医学的権威が従属させ、精神鑑定に用いられる言説を家庭にまで侵入させた権力、それが「正常化=規範化」権力であり、政治的権力の一様相である。
こうした権力の過程への侵入は、令和四年に施行された岡山県家庭教育応援条例の言説にはっきりと見られる。子に対する家庭教育と学校・社会ルールの連続性を打ち立てること、それも幼児期から。特に幼児期において正常な発達を阻害する障害を、事業者と連携していち早く見つけ出し、矯正しようとする狙いが見て取れる。事業者というのが具体的に何を指しているのか不明瞭にして条文が成り立っているが、おそらく子供の障害に関する矯正をなす司法=医学的な専門家のことを指していると思われる。逆に親に対しては社会からの孤立を防ぐことをキャンペーンの狙いとしている。しかし、応援条例と言いながら「保護者は、家庭教育を充実させるため、学校等と連携するよう努めるものとする。」とあるようにしっかりと親への義務を課している箇所も見受けられる。この条例は親と子の双方へのアプローチである。そして、はっきりと家庭への「正常化=規範化」権力の介入を目指している。私はこうした権力へ対抗する別の権力を創造したいという願望をもっている。それは無縁という、孤立とはまた異なる権力であってほしい。
「犯罪でもなく、病気でもなく、異常なもの、異常な人物を管理する医学的で司法的な審級が精神鑑定によって構成されるかぎり、まさにそのことによって、精神鑑定は重要な理論的かつ政治的な問題となります。」
「正常化=規範化」権力は、この異常者ないし障碍者を、ハンセン病患者を社会の周縁へと追いやって社会から見えなくする形、つまり排除というネガティブな実践を用いて権力を行使するのではない。フーコーは、排除や抑圧といったネガティブな実践を政治的権力の行使できる限界と位置付けている。つまり、排除や抑圧といった方法は権力の及ぶ限界のところに用いる最終手段であり、不効率な実践なのである。社会ならびに家庭に対して、「正常化=規範化」権力は排除や抑圧といった方法を行使することはない。排除や抑圧といった方法で異常者や障碍者を見えなくする形で権力を行使する代わりに、「正常化=規範化」権力は異常者や障碍者を社会の中で目に見えるように言説を管理する。ポジティブな実践によって、つまり矯正や社会復帰といったキャンペーンによって、異常者や障碍者についての特徴を各人が語りだすように言説を社会に溢れさせる。社会の中に異常者や犯罪者、変質者や障碍者といった者は、社会の構成者自らが進んで見つけ出せるようにして、それまで排除していた者たちを、いたるところに出現させるのである。それも私たちの手によって。言説は、各人が目にした自分とは異なる異常性の特徴を複写して他人に伝達するように、広がってはいかない。各人が感じるのはせいぜいその人に対する嫌悪感であろう。それは自分との同一性の亀裂を感じるにすぎないだろう。逆に、言説は、同一性の亀裂に耐えられなくなった場所に、その溝を埋めるために、借りられてくるにすぎない。ゆえに、言説とは必ず他の言説であり、聞き伝えなのである。そしてその聞き伝えを、同一性の亀裂の溝に用いることによって、私たちは異常者を出現させるのだ。つまり、異常者とはそのひとに一方的に付けられた名前であり、「キモイ」というのも、感情ではなく、対象を出現させるために付ける名前なのである。ドゥルーズの言うように、言語は、自らが見たものや感じたことを他者に伝えるだけでは言語とはならない。自分が聞いたことを、第三者に伝えて初めて言語となるのである。また、言語は信じるためにあるのではなく、従わせるためにあるのである。「あいつは異常だ」と言うとき、それはその人物を異常者だと自分にも第三者にも信じ込ませようとしているのではない。もちろん共感を期待する要素がないというわけではない。しかし、第一に言語は、「あいつは異常だ」と言うことによって、第三者そして自分にも、「あいつが異常である」ことを伝えているのであり、それは既に聞き伝えなのである。ゆえに異常者は発見されるのであるが、それは再認=再現前化によるものなのである。そして、第三者にも再認=再現前化にっよって異常者を作り出すように命令しているのである。その結果として共感が付随することもあるだろう。再認=再現前化した異常者を各人が排除するネガティブな形で主体性は形成される。しかし、「正常化=規範化」権力の各人への浸透はといえば、つまり異常者や障碍者に関する言説の伝搬は、笑いを誘う言説の愉快さをもって、ポジティブな形で浸透していくのだ。異常者は見えなくなるのではなく、常に見える形で隔離され、各人をその隔離された側へと自分が追いやられるのではないかという恐怖をそこに留まらせる。「正常化=規範化」権力は、
「排除によってではなく、むしろ緻密で分析的な封じ込めによって作用する権力。雑然とした大きな集団への分割によってではなく、個々人の差異にもとづく分配によって作用する権力。誤認に結びつくのではなく、逆に、知の形成、その充当、その蓄積、その増加を保証する一連のメカニズムに結びつく権力」
である。
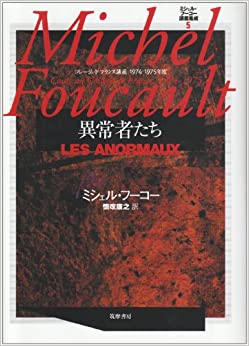
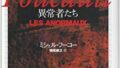
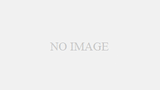
コメント