イリイチは、自立共生的な再構築には今日の政治目的を逆倒することが必須だとし、それが人々の生き残る唯一の手段だと考える。
道具の使用が、今日の政治的目的である経済発展の手段としてそれに従属する限り、道具の使用そのものの楽しみはその目的から疎外されつづける。つまり、道具の使用ないし道具と関係する身体という道具の使用にともなう生産の楽しみは、それ自体を目的とすることがない。
千葉雅也氏は『勉強の哲学 来たるべきバカのために』において、身体の使用において、それが自己目的的である代表的なものにダンスを挙げられている。ダンスは身体という道具の使用を通して何か別のものを生産するわけではない。その使用自体が生産そのものであり、その内部に楽しみが宿るのである。さらに千葉氏は、書くことについてもその書の中で触れている。
「アイデアを出すために書く。アイデアができてから書くのではない。」
つまり、書くことが、脳内にできあがったアイデアを表現するためだけにあるのならば、書くことは書かれるべきものに従属するゆえに自己目的的ではない。しかし、千葉氏は「書くこと」は知っていることと知らないことの境界でなされる行為だと説かれている。つまり、私なりに解釈すれば、アイデアとは知っていることと知らないことの間の架け橋のようなものであり、書くことによってアイデアが形成され、知らないことへと繋がっていくということであろう。その意味で、書くことは、表現に従属する手段とは別様に「知ること」という学ぶ楽しみを目的としており、ダンスと同様に自己目的的でもあるのだ。
「書くことこと」がたんに表現の手段になっているのが、現代の病である。そこには、スマートフォンという道具が使用されているのだが、それはもはや文章を「書くこと」ではなく、「打つこと」になってしまっている。「打たれたもの」の一部は動画や画像といったより視覚に訴えるものに従属する補足文や広告文である。「打つこと」には、余白がない、偶然がない、ともいえる。それは、あらかじめ完成している商品やサービス、さらにはコミュニケーションやそれに伴う感情表現を打つのであり、「書くことに」の内部に宿る「知ること」、別の言い方をすれば、筆先に宿る未だ知らないことは「打つこと」の内部には存在しないのだ。また、そうした「打つこと」は打たれたものに従属するだけではなく、そうした打たれたものへの他人の反応へも従属している。「打つこと」に自己目的的な要素が欠けている限り、それに依存することは、相対的に「未知のものを知ること」が「自分のしたことから学ぶ」ことから「他人によって打たれた情報の受容」へとなり、そうしたサービスへの依存が増すことになる。
ダンスと同じように、ペンを持つこと、さらには工具や料理道具、楽器の使用それ自体を楽しみ、自分がしたことから学ぶことが自立共生的な生活スタイルを構築することの魅力である。こうしたスタイルの形成は、趣味という産業主義的社会の余暇としてではなく、産業主義的社会そのものの転覆の萌芽とさえいえるのだ。
スタイルといって私が真っ先に思いつくのは、スケートボーダーたちである。かつて彼らのスタイルを不良と呼ぶのがふさわしい時期があったと思う。スタイルとしての不良は、しかし、社会の中に取り込まれていないという限りにおいて「力」となる。それは、「はみだし者でかまわない」という自覚によって「力」となるのだ。しかし、社会は、そうした「力」を解体すべく、オリンピックの競技化という手段をもちいた。彼らすべてを経済活動の中に放り込むことが主要な目的ではない。一握りのスター選手と犯罪者という両極を彼らのスタイルの中に組み込み、「力」を削ぐことがその目的である。スタイルとしての不良は社会の外に存在しえても、犯罪者は社会の中でしか存在しない。ここでの「力」とは何か?それは師と弟子の関係がスタイルの中に存在することである。スタイルの外で評価されることを必要としないのだ。それは居場所と呼んでもいいだろう。彼らのスタイルはそんなに弱くはないであろう。彼らが、集団になって形成しているものこそ、スタイルである。憧れと怖さ、私が少年期にスケートボーダーたちに持った感情である。有名であるから憧れるというのはスタイルには全く関係のないことである。また、スケートボーダーたちに、それは趣味ですかと聞くなら、否と答えるだろう。そうしたスタイルを、私たちは身近にたくさん形成できるはずである。
しかしこうした道具の使用の魅力だけでは、たいていの人々が今日の社会構造の中に自己イメージを持っている以上、そうした社会構造=環境コード、つまりは「こうするべきだ」の外に出て、自立共生的な生活を目指すことが難しいのも事実である。
しかし、粘り強くその魅力について考え、実践していかなければならない。
自立共生的な社会を可能にする条件とは
(1)道具の使用の自由
(2)専門化によるサービスないしそうした人々が提供する専門的道具、さらには電気やガスといったエネルギーの需要依存からの可能な限りの脱却
(1)と(2)は、互いを補完しあい自立共生的な社会を可能にする条件となっている。
今日用いられている工業生産的な大規模道具、家庭における機械化された道具たちは、その使用において生産されるものが、生産する以前において既に完全に決定されており、その生産過程において偶然が起こらないように徹底的に管理されている。そうした道具の対極にあるような100円均一ショップの道具さえも、使用者を自由にすることはない。なぜならば、100均の道具は使用用途において非常に細分化され、便利ではあるけれど、大規模道具や家庭の機械道具と同様に使用者はすでに決められた仕方通りにしかそれを扱えず、また他の道具との協働によるアレンジメントも不可能になっている。ゆえに使用者はあくまでも使用者のままであり、自律的に生産する楽しみを持ちえない。
今日社会から提供される道具の多くは、使用者に選択権を与えず、使い方が一律に社会構造の内部にコード化されている。その結果、より良いサービス、より良いものは専門家や大企業から与えられる通りに、それを享受するということになる。これは隷従である。そうした、専門家や大企業が作る新たな帝国主義への隷従である。そしてそれは従属しているという感情さえもつことなく、それを享楽し、その内部でしか自己イメージを持つことができなくなっている。それゆえ、ダンスは自由がなく、ぎこちなく、一律なものに凝り固まっている。しかし、そうした一律で逸脱する者のいないダンスは北朝鮮の人々のダンスに似ているところがある。そうしたダンスがまた管理をより容易にするのだ。
スマートフォンがその代表例だ。それは確かに人との繋がりを生み出し、使い方の自由を使用者に提供している一方で、消費の好みを逐一解析し、人の行動、位置、存在そのものを大規模に管理し、大企業の専門家ないし政治家にその使用の権限を提供しつづけてもいる。その行く末は、今見た通り、みながみな同じものを好むようになり、同じ店の行列に並び、同じようなものを楽しみ、また同じものを恐怖し、嫌悪し、それに対し防衛する方法を各人が持ちえず管理者に全てを丸投げするように仕立て上げられていくのだ。
ゆえにこのような専門家が提供するサービスや商品への需要依存から脱却するためにも、自らが道具のある程度の支配者となって、その道具とともに生産を楽しみ、ダンスを楽しむ必要がある。
道具の使用の自由とは、ある程度ではあるが自らが支配者となりうる道具の使用においてこそ成立する。そうした道具は、もちろん手工具のようなものがそうしたものとなりえるだろう。しかし、人々を自由にする道具というものを手工具に限定する必要はない、楽器も道具であり、食物や木材も材料というだけではなく、ある場合には道具とさえなりうる。楽器と食物と身体は、互いに関係しあい、機械状のアレンジメントを形成し、音楽と料理で客をもてなし楽しむ、おもてなし機械を生産しうることもあるだろう。そうした機械は「おもてなし」を手段とは決してしない。「おもてなし」そのものが楽しみなのであり、金儲けや経済発展とは一切関係しない。
自立共生的という観点からみて、良い道具というものを考えるならば、それは可塑的で変化しうることのできる道具ということになると思う。変化は他の道具との協働によって生じる。身体というものも一つの道具であり、機械であり、他の機械との協働におけるアレンジメンとによって自身の位置を変え、働きを変える。ゆえに身体という機械は中心的であるが、それ自体不変の支配者ではないこともわかる。道具との協働において、調子が悪いときそれは、道具や道具を通して見る社会、そしてその社会の反映によって作られた自己イメージに原因を探りたくもなる。しかし、調子の悪い理由を他者のせいにする必要もなく、はたまた自分のせいにする必要もない。道具をうまく使えない理由を、身体のあらゆる器官からなる自己なる一つの有機体に還元し、頑なに自己でありつづけること、または自己を放棄する必要はない。道具との不調は身体との協働の不調であり、その不調の箇所を徹底的に見つめるだけでよいのだ。そこには他者も自己もない、機械同士の関係しかないのだ。その機械同士の関係をよく見つめ、毎日すこしずつ改善していく必要があるのだ。この意味でも、「自分のしたことから学ぶ」ということの重要性が見えてくる。もっと言えば、自分など取り去って、機械同士のしたことから如何に変化が起こりつづけるかが重要なのだ。身体という機械は、ある程度の支配の自由を必要とする。しかし身体機械による他の機械の管理から楽しみが生まれることは決してない。身体機械は他の機械とのアレンジメンとによって戯れ、自らが変化することによって楽しみを生じるのだ。身体は何かに従属しても駄目だし、自己に従属しても駄目だ。また何かを従属させても駄目だ。自己さえも。そして、この身体のダンス、それがなしうることの限界こそが節制でもあるのだ。この節制は、サービスや商品の需要依存からの脱却を可能にする条件でもあるのだ。
「自立共生的な社会は、他者から操作されることの最も少ない道具によって、すべての構成に最大限に自律的な行動を許すように構想されるべきだ。人々は、おのれの活動が創造的である程度に応じて、たんなる娯楽とは正反対のよろこびを感得する。一方、道具が一定の点を超えて成長すると、統制・依存・収奪・不能が増大する。私は“道具”という言葉を、ドリル、ポット、注射器、箒、建築材料、モーターのような簡単なハードウェアだけを、また自動車や発電装置のような大きな機械だけを包含するのではない、広い意味で用いる。すなわち私は、コーンフレークとか電流とか蝕知しうる商品を製造する工場のような生産施設と、“教育”とか“健康”とか“知識”とか“意志決定”とかを生みだす感知しえない商品の生産システムとを、道具のうちに含めるのである」
上記の原則から、イリイチは自立共生的な道具と、それを阻む操作的な道具とを二分する。
イリイチの考えを基にすれば、自立共生的な道具と操作的な道具との区別を以下のように見ることができる。
自律共生的な道具
・誰にでも自由に使える
・自分が道具を使用した経験そのものから学びを得る
・価格と維持費が安い
・環境破壊が少ない
・自分が必要なだけの生産物を産み出す
・他の道具によって代用できる
操作的な道具
・資格を必要とする(その結果、資格が有する専門家が提供するサービスを受容せざるを得なくなる。これは自己の無力感を生むことになる)
・教育という形で道具の使用を学ぶ
・価格と維持費が高い
・環境破壊が大きい
・規定された仕方通りに操作する、操作的な道具同士がネットワークを形成している(高等教育-医者、初等教育や中退-工場労働者)
・必要を超える形態(高性能、多機能、傷や汚れがひとつもない)で大量に生産物を産み出す。
・他の道具によって代用できない。その道具を使用しない限り、他の道具に接する機会さえ奪われている。
自由に使える道具にとって、容易に使えることはその条件であるが、それだけで十分ではない。自由に使える道具とは、その道具を使うのに卓越する余地を持っていなくてはいけない。卓越とは、その道具を介して、他の道具にいかに働きかけることができるようになるかということであり、その卓越度によって、他の道具と創造的かつ自由に繋がりうるかが決定される。ゆえに、自由に使える道具とは、容易に使えない道具であるとも言える。しかし、それは自立共生的な道具にとって矛盾ではない。なぜならば、容易という意味での自由に使える道具とは、操作的である場合が多いのだ。その使用を半ば強要されているがゆえに、使い方は容易にされている道具をよく目にする。そうした操作的な道具は、別の操作的な道具とあらかじめ結び付けられており、各人の自由を奪っている。自律共生的な道具についてイリイチは以下のように述べている。
「そういう道具は使用者がまえもって認可をとることを必要としない。そういう道具が存在するからといって、それを使わねばならぬ義務が課されるわけではない」
道具の使用に認可が必要になると、その道具の使用法を習得するために教育という別の道具を介さなくてはならなくなる。教育という道具は義務として課されるのである。結果、教育を終えるまで、その道具は得体のしれないもののように思われる。これは、専門家が提供するサービスを価値あるものと思うようになることの構成要素のように思われる。
学ぶことは、教育ではなく、道具の使用においてなされるべきである。そこにおいて、自分のしたことから学ぶという機会がやってくるのだ。そのためにも、教育を受ける前に、道具を触ってみなくてはいけない。それは、教育と資格に慣れきっている私たちからすると、命がけの飛躍をするほどに怖い。しかし、別の世界へと踏み出すためにはドアを開かなければならない。道具に触れず、そこから遠くを眺めているだけでは、完成した商品やサービスしか知ることができないであろう。ある種の自立共生的な道具は、商品やサービスを排した世界の中へ私たちを誘うのである。
義務とは強制することであるが、それは直接に課すことと、独占によってそれを使用せざるを得なくし、間接的にその道具の使用を強制することの二通りがある。
教育とは直接課すことである。教育がなければある種の職には就けないようになっている。教育は、その達成において資格というゴールが設定されている。そうした一連の過程がパッケージ化されているため、代用が利かない。しかし、学びは、ある学びを捨てて、他の学びへと移ることもできるし、学びを深めることによって、他の学びと、偶然的に出会うこともある。しかし、教育課程には、そうした偶然は存在しない。教育とは、自分がしたことから学ぶといった、学びにおいて道具とともに、学ぶ主体である自己自身が変化することはない。さらには、情報で自己を満たすことも、教育においては二次的なものに過ぎない。教育において、もっとも重要なのは、静かに待てといったら静かに待ち、用紙を裏返せと言ったら裏返し、回答はじめと言ったら、一斉にテストの回答を始めることである。つまり従わせることである。従ったものと従わなかったものを選別し、一方に教育の成果物である資格を与え、他方に落伍者の烙印を押す。そして落伍者であることを自認させる。さらに悪いことに、落伍者には無教養なのだから仕方がないという、無力感すら与える。
義務とはまた、社会の空気の力を借りて、ある種の道具を独占することによっても生じる。以下でその説明をしていく。
操作的な道具は、自律共生的な道具によって代用させないようにあらかじめ計画されて作り出されるケースを最近よく目にする。その一つには、高度なセンサーを内蔵した自動車や家電製品が挙げられる。そうしたものには手厚い補助金がついて販売されているが、壊れてしまえば(実際壊れやすく長く使用できないように計画されて製造されている)、決して自分で修理することができず、その修理が独占されている。その二次的効果として、単純なペンチやねじ回しを無用な道具に変えてしまっている。ペンチやねじ回し等の誰にでも自由に使える道具は、それ自体性質を変えることなく、相対的にその価値を下げられているのである。
もうひとつは行政手続きの問題である。マイナンバーカードが国民の管理を強化することは明らかである。マイナンバーカードに代表される操作的な道具は、それを受け入れ、所持すること自体に恩恵があるのではない。またそれを各人が使用して自由を生むのでもない。逆に、それを持たない限り、他の道具に接する機会が奪われるように設計されている。それが問題なのである。これは自立共生的からは真逆の制度(=道具)である。こうした行政政策は、コロナワクチン接種の政策から学んだことだろう。接種歴のある者とない者の選別、接種歴のある者への優遇と接種するか否かは自由というこのパッケージ状の道具である。「一方への優遇」と「選択の自由」のパッケージ化は国民を分断する。それが、命と財産に関係するから尚更である。
もちろん、マイナンバーカード自体が絶対的に操作的な道具であるわけではない。絶対的に操作的な道具など存在しない。道具は、それぞれあらかじめ目的をもって作られる。車は早く移動するために、電子レンジは食物を加熱するために、これらの目的に管理的要素は見つからない。しかし、道具は、道具同士のつながりによって、相対的に操作的になりうるのだ。道具同士のつながりは一本の糸のようにではなく、網目状をなして私たちの生活の中に形成されている。車はショッピングモールと電子レンジは加工食品やコンビニ弁当と。コンビニ弁当はそれを配送する車と、といったように。こうしたつながりが、経済的な社会的道具の網目を形成している。車は私たちを好きなところに連れていき、その中に、お得ということで大量に購入した食品を詰めて家へと持ち帰ることもできる。そうして運ばれた加工食品は、大きな冷蔵庫に保存され、いつか電子レンジで調理されるのを待つ。私たちは好きな食べ物を、便利に、早く、お得に食べることができる。これも一つスタイルであるが、言うなれば消費者というスタイルである。消費者というスタイルは、車や電子レンジの所有によって、他の道具と容易につながることを知っている。しかし、車や電子レンジの所有によって、私たちが欲望するものを経済的社会的に作り上げられていることには無関心である。私たちの欲望を作り出すのが、経済的につながった道具であり、そうした道具のつながりが網目状の操作的な道具を作っているのである。
先にも述べた通り、マイナンバーカードは、それ自体が操作的な道具とは言えない。しかし、消費行動が、楽天経済圏やドコモ経済圏などと呼ばれるポイント制度によって形成されているのと同様に、マイナンバーカードは、財産と生命、消費行動に限られない人生そのものを独自の経済圏の中に取り込もうとしている。マイナンバーポイントはその運用の一部である。長く健康で仕事をして生きればポイントがもらえる。そういうことも起こるだろう。しかし、こうした操作的な道具においてもっとも重要なことは、人生そのものを経済圏に入れることである。どう行動すれば、便利で、お得かということを、個々の行為にではなく、人生そのものにまで適用しようというのだ。人間の人生はすべて消費者の人生となる。その結果、消費者は容易に操作され、各人一律な行動を余儀なく形成させられることは、以上の説明からも理解できるだろう。何歳になったら何をしなければならない。何歳まで働けば将来得する。
自立共生的な生活は、自律共生的な道具によって、自発的で創造的な生産をすることで、消費者のスタイルとは異なったスタイルを形成できるはずだ。家具職人のジェームズ・クレノフは『木の家具 制作おぼえがき』において以下のように記している。
「私たちは木材の言語を発見しようとしている。それは私たちの工芸の言語でもある。私たちの道具が最上の状態にあれば、その時には道具は道具ではなくなり、私たちの心の最奥部の意図に合わせて調律された楽器となる。ちょうどそれと同じように、木材を相手にする時も、木材と私たちの心の内奥は同調する。一つの発見がもう一つの発見へ、さらには次の発見へと連なってゆく。一つ一つの発見は気づきにくくもあり、見るからには些細なものかもしれないが、最後にはそれが全体の一部となる。——その全体は、人が制作する時のその人自身の全体性である。」
自分がしたことから学ぶということを体現した人であり、スタイルを確立した人でもある。この家具職人を私は大変尊敬する。
「私がこれらのものを作ろうとするのは、作りたいからであり、木材を愛するからであり、精緻な道具を持っているからだ。そして、私はただ制作をし、喜びをもって制作をし、どんなに長くかかろうとも、常にいつも学ぶ姿勢をもとう」
未だ知らないことを教育によって知るならば、それを知ってしまえば満たされてしまうだろう。しかし、クレノフは制作物によって、自信を回復した時でさえ、むしろその瞬間に、緊張と矛盾を感じると述べている。
この緊張と矛盾は、アイデアというものが常に私の外部にあり、それをどうにかして取り込もうと必死になることによって生じるのではないだろう。自発性ということの本質的な差異はここに見られるのだろう。アイデアとは自己の欠落を埋めるものではないのだろう。逆に彼にとって、アイデアとは欠落そのものなのではなかろうか。それは制作の外部からの抑圧ではなく制作の内部から生じてくるものなのだろう。内部からの抑圧とは何か?彼にとっては木材と対話なのであろう。それが未知のものへと自己を駆り立てるのではなかろうか、すると創造的という言葉の意味も変化するのではなかろうか。
「非独創的な自己を受け入れるのに時間がかかった」
とも彼は記している。私は非独創的な自己を受け入れるということが責任をもつことなのではないかと思う。未だはっきりしたことは分からないが、その内部から出られないということによる謙虚さや、節制=コンヴィヴィアルなのではなかろうか。それがスタイルであり、固執ともいえるのであり、翻って独創的とも言いうるのではなかろうか。
テレビもまた、何を映し、それをどう切り取るかを容易に選択できるため操作的な道具として使われている。ブルデューは『メディア批判』において以下のように述べている。
「テレビは、雑事件に重点を置いて、この貴重な時間を空白、無あるいはほとんど無に近いものによって埋めてしまっているがゆえに、市民が自らの民主的な権利を行使するために持っていなければならないはずの適正な情報排除してしまっているのです。」
「テレビは、見せながら逆説的に隠すのかということです。テレビは、隠しています。それが行っているとされていること――つまり情報を与えること――をするためには見せなければないはずのものとは違うものを見せることによって隠しているのです。あるいは見せるべきことを見せるとしても、人々がそれを見ないようなやり方で、あるいは現に見せているものが意味を持たないようなやり方で見せることによって、隠してしまうのです。あるいは、見せているものが現実とはまったくかけ離れた意味を帯びるように構成することによって、かえって隠してしまうのです。」
コロナウイルスが恐ろしいということを映し、不安を煽り、ワクチン接種を呼びかけるが、それによってワクチンの危険性を隠すのもテレビが操作的である理由である。また、報道を突然しなくなり、危機はすでに去ったものとし、存在しないかのように印象づけることも可能である。その結果、その存在と同時に政策の良し悪しすら検討されえなくなる。
地震速報は、巨大地震や津波の到来を数秒から数分早く知らせることができる。しかし、その数秒の時間稼ぎのために莫大な研究費とシステムの維持費を必要としていることは隠されている。また、テレビは地震速報や災害の恐ろしさばかりを映す。それによって人々は、その放送から自分に何ができるかを学ぶのではなく、自己の無力感ばかりを増すことになる。せいぜい、学べることといえば、いざという時のために、何を準備しておけば良いかということぐらいである。これが映すことによって、本来必要とされるものを隠すことである。その結果、他の操作的な道具と同様に、テレビも、視聴者に専門家が必要であるという観念を植え付けるのである。地震研究の専門家、災害の専門家、自衛隊など。
もっとも大切なことは、被災したときに誰が自分を助けてくれるかであり、誰を助けることができるかである。
慰霊や語り継ぐことの重要性を報道することによって、現在も苦しんでいる人々を隠す。また、現在も苦しんでいる人を映すとしても、それは募金という決して苦しんでいる当人の手助けにはならない方法を提案する。また、「支援」や「語り継ぐこと」という言葉でほとんどと弔いと同じ感情を抱かせることによって、無力感を抱かせると同時に責任から解放しもする。
また、SDGsやサステナブルという言葉の繰り返しによる放送は、環境問題を取り上げ、映すことによってその本質を隠す。本来エコロジーなる活動は政治的活動であり、産業社会における成長とは相反するものである。しかし、産業社会の成長の中に環境問題を取り込むことによって、産業社会が必然的に避けられない環境破壊やそれをごまかす為の莫大な処理コストを隠す。そして、視点を各人の意識的な行動へと向け、それを促進することによって、社会構造そのものの転換の必要性を隠しているのである。
道具の網目の一部が、もはや自発的な想像によって、他の道具によるアレンジメントによって代理されえず、そのサービスの需要に依存せざるを得ないとき、その網目の部分を構成する道具たちは操作的となることを見てきた。その網目の部分を生活から除去する方法として、スマホやマイナンバーカードや車やテレビなどの、操作的道具の網目を構成する主要な道具の所有を廃棄することによって、各人がその網目に穴を開けることは可能だろう。しかしすぐに生活が立ち行かなくなるだろうし、結局はそうした道具が繋がるサービスの価値観をより増強することにしかならないだろう。ゆえに私たちは、道具の繋ぎ変えをし、道具のアレンジメントを行い既存の価値と交換しなければならない。その結果が操作的道具への需要依存から自らを解放することになるだろう。それは各人の物や食物の生産、さらには、学び、医療、介護、死に至るまでに、自発性を取り戻すことになるだろう。
加工食品を手料理に置き換えること、スーパーの買い物を八百屋、肉屋、米屋、パン屋の買い物に置き換えること、それを時間の節約やお金の節約のために行えば、きっと既存の価値が勝利する。ゆえに別の次元の道具の網目と繋ぎ合わし、アレンジメントを行わなくてはならない。その一つがが車の使用を自転車の使用に置き換えることによって、小さな商店を周る手段を得ることである。これは既存の価値と真反対の不効率な道具のアレンジメントである。しかし、それは買い物という行為に、車で外出し、車道を走行し、スーパーのパーキングに止め、無人のレジで支払いを済ませ、ガソリンを入れて、家に帰宅するという、ほぼ規定通りの、道具の操縦者とは異なる次元を追加することになる。それは商品を選ぶことのアレンジメントとは次元が違う次元を、買い物という行為に繋ぎ合わせるのである。それが誰から買うという次元の自由である。そこには自発性の自由がある。自発性の自由とは顔であり、それは手を差し出さざるを得ない責任であり、手を差し出さない責任でもある。したことによって学ぶことは、それが習慣になるまでは、常に不効率を通過せざるを得ない。もしかしたら、一生涯不効率が続く可能性すらある。だが、それがスタイルを作るのだ。ストリートダンサーやスケートボーダーのようなスタイルを街の至るところに見ることもできるだろう。若い身体をもたずともスタイルは形作れるのだ。しかしスタイルは各人だけでは不可能だ。それは各人の自発的想像の限界によって、他者の自発的想像を求める、その境界に生じるのだ。それは世間やサービスを求めるのではなく、自己の限界によって誰かある人を求める。
原子力発電、コロナワクチンやマイナンバーを批判するならば、それを肯定する者を批判してはいけない。そうすれば管理者の思うつぼである。批判すべきは、それ自体の科学的安全性、さらにはそれが操作的な道具として国家から提供されること、そして、それに頼らざるをえない現在の自己自身である。そしてそれは、まず操作的な道具を形成する道具に自分がどのくらい依存しているかに向けなければならない。もちろん、その方法は、各人が想像するべきだが、その基礎となるのは、そうした道具への需要依存を減らし、自律し、少数派を形成することだ。
少数派とは何か?それは自分自身に責任を持つことである。サービスに依存するのではなく、生活に必要な道具を自分自身で制作することであり、その限界において、名をもつ誰かと出会い、その誰かに依存し、そうした少数の顔の見える依存先を増やしていくことである。それがスタイルを形成する。スタイルは決して一人では成り立たない。このことから、少数派とはスタイルであるといえるのではなかろうか。
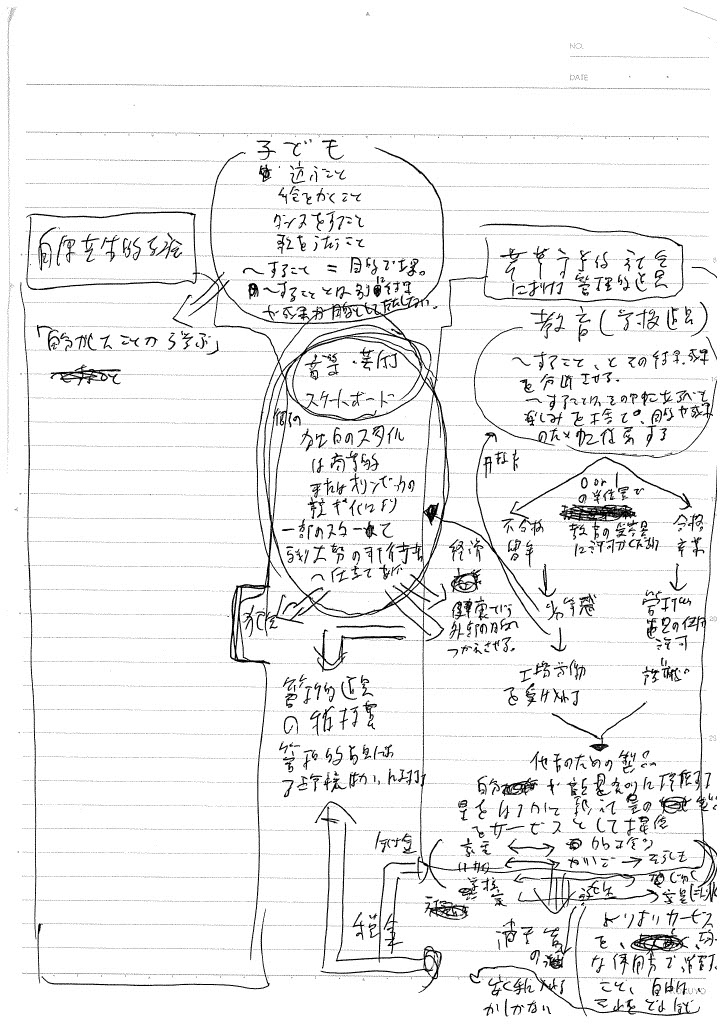
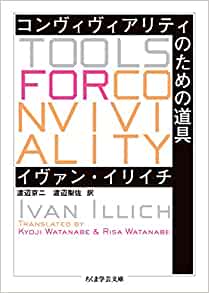


コメント