クライシス(転機)というギリシア語に由来する言葉は、「選択の道」、「分かれ道」を意味してきた。しかし現在では、「ドライバーよスピードをあげろ」を意味するようになったとイリイチは言う。クライシスは、スピードを上げるが故に必然的な襲いかかってくる脅威を含み、それに対する受動的な反応を呼び起こさせる。速いスピードで変化するものの外に放り出されないように、また必然的に生じる摩擦や事故の不安から身を守るための安全ベルトの必要性を感じさせるのである。この世界が各人が適応できるスピードの限界を超えて変化するとき、各人は適応を断念し、専門家と呼ばれものに保護を求めるようになるのだ。それは財産や労働力、管理の力を一部の人間へ結集することであり、私たちが容易に操作されるようになることを意味する。
適応という言葉を使ったが、そもそも適応というもの自体が受動的であり、変化に対して後手に回っていることを含意する。その点で、クライシスに従属し、かつクライシスに対しては必然的に各人の自律的な適応の不可能性が宿命づけられている。ゆえに、私たちは「管理」に保護を求めるのを退けると同時に「適応」をも問い直さなければならない。
この世界の変化は激しく津波のようにクライシスは襲ってくるだろう。内田樹氏は「後手に回るな」というブログ記事を書いている。その中で、後手に回ることを、相手が何かを仕掛けてきたので、それに対して最適な対処をすること、と書いている。これはまさしく現代的貧困のことを言っているように私には思われる。つまり、学歴社会、専門家の乱立とは、あらゆる脅威に対して私たちが後手に回っていることを前提として、それに最適に対処する手段の保持が重宝されているが故である。それはまさしく、脅威に対して先手を打ったり、そもそも脅威が近づいてこない生活が不可能になっていることの裏返しである。
内田氏は「先手をとる」というのは「場を主宰すること」と説いている。場を主宰することは、相対的な優劣を競うことを止めるための場を作り出すことである。内田氏は、合気道の道場を作られ、修行の場とした。修行というのは先たつの背中を見ながら歩むことであり、優劣を競わず、到達不可能な目標に向かって精進することである。なぜそれが先手をとることなのかというとが知りたいところである。もちろんのこと、場を主宰したところで、未来を予知できるわけではない。だが、未来とは私たちに押し寄せてくる世界の変化そのものではないだろう。未来とは世界の変化に対する私たち各人の反応的行為である。それゆえ、場をもたない場合、押し寄せてくる激変の波から身を守るために、専門家の管理に身をまかせて、その人たちが勧める通りに行為し、また保険をかけつづけることになる。場をもっていたとしても、脅威が消えることはない。しかしながら、未来は決まっていないと言える。クライシスの本当の意味を取り戻すのはこのときであろう。つまり、世界の激変に対して、反応しない、もしくは敏感に反応しないことである。矛盾するようだが、「先手をとること」は、未来に対して「後手をとる」ことだと言えるのである。立ち止まり、本当の意味でのクライシス(転機)、つまり選択の道が開けるの「場」の中においてなのである。内田氏は、師匠から道場には変なやつが来ると伝えられ、実際に道場を開くと、人生を変えるために入門してくる弟子に幾人も出会ったと、別の記事に書いている。このことからもクライシスは場の中で開かれるのだと思われる。
私は「場」が道場に限ったものではないと思う。工房にも、食堂にも、ライブハウスにも場は宿るのだと思う。もちろん他の場所にも。イリイチは、クライシスを「ドライバーよスピードをあげろ」という意味を持つ必要はないと言う。そして以下の文章をつづけている。
これまでと違う生活の可能性に気づくあのすばらしい刹那
この刹那が「場」において生じるのであるから、まずは「場」に飛び込み、いつかは「場」を主宰するような人間を目ざさなくてはならない。場が導くものは、もちろん優劣を競わないことである。でもそれは結果であり、その過程には邪視を捨て去ることがあるのだと私は解釈している。邪視を捨て去ることそのことの過程こそが修行ではなかろうか。邪視とは相手を羨んだり、妬んだり、または見下したりすることであるが、それは邪視の表面的な効果でしかないように思われる。邪視とは、根本的には自らに向けられた眼差しの一種であり、それによる相手を眼差さない、眼差せないことであると最近感じている。修行で得られる自信というものも二次的なものでしかないように思われる。修行で得られるのは、むしろお道化ることや、ユーモア、話すことなのではないだろうか。これらのことが、邪視や仮面といかに関係するのだろうか?
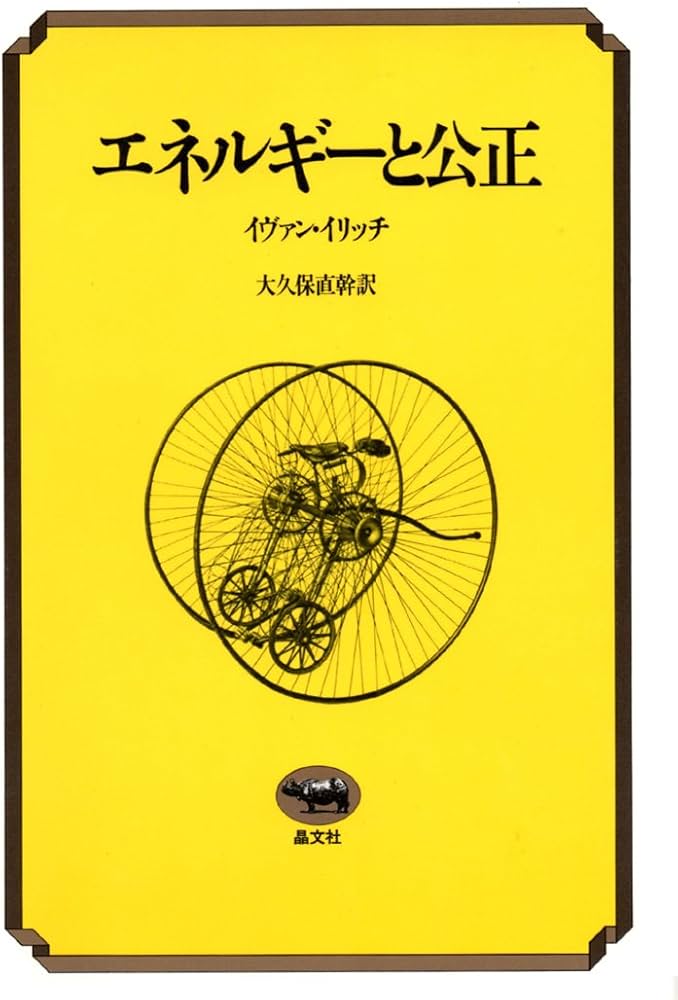
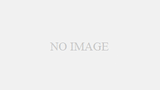
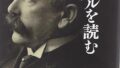
コメント