「中等後の学校教育、成人教育、予防医学、幹線道路、電線を張りめぐらした包括的な集落に万人が近づくことは、まだ立派な目標であった。今日では、教育、運輸、健康ケア、都市化などをめぐって組織化され、神話を作りだす大祭儀が部分的ながら解明されてきた。だがそれはまだ打破さてはいない。」
「専門家の意見によって権利が形づくられる社会では自由が衰退していくことを、看取せざるをえなかった。商品の生産を高める新しい道具か、それとも使用価値の産出を可能にする同じく現代的な道具か、大量生産される商品を手にする権利か、それとも満ちたりた創造的な個人の表現を可能にするための高度の自由か、金銭的な利益をえる雇用か、それとも有為な失業か、これらの二者択一についてわたしは考えぬかねばならなかった。そして、他律的な管理を選ぶのか、自律的な活動を選ぶのか、その選択の個々の次元で、われわれに後者を主張させるような言語を努めて回復しなければならないと考えたのであった。」
現代化された貧困とは、規格化された大量製品の産業的生産およびその使用に依存するがために、自律的に活動し、創造的に生きる能力を失っている状態である。こうした貧困は、行為することが、名詞化され(就活、婚活、妊活、腸活、終活)、それに付随する商品やサービスによって周りを取り囲まれてパッケージ化され、つまり規格化され、それをそのまま受け入れて消費するだけに万進することに一因がある。
こうした状況では「学ぶこと」さえも教育、生涯学習、資格取得などのように名詞化され、就職と関連付けられて商品化される。現代以前の「学ぶこと」が「自分がしたことから学ぶ」ことだとすれば、現代の「学ぶこと」つまり教育は「学んだことの所有」つまり「社会的有用性を保有しているとされることに対する信用の蓄積」へと姿を変えたのである。「自分がしたことから学び」そして生きる。学ぶことと生きることは、分離されず、重なり合っていた。そうした状態では、自分がしうることでしか生きていけないがために、死と隣り合った貧困が傍にあった。しかし、それは現代的貧困とは呼ばない。
私たちは、現代的貧困に気づくだけでなく、この現代以前の貧困に身を投じうるときにのみ「コンヴィヴィアリティ=自律共生」が可能となるのだろう。それは自分がしたことから学び、それによって一人孤独に生きることを意味する。しかし、それだけでは生きてゆくことができないがために、他者と協働し繋がりあう必要が生じる。孤独は孤立ではない。孤独は、自分がしうることの少なさに気づき、それから解放されるために産業的生産に身を投じるのではなく、孤独に向き合い生きることである。孤独とは決して名詞化されて一律の意味を得た社会的排除状態、哀れな状態ではない。孤独とは孤独を生きることなのだ。そして、生と死のはざまで他者とつながることである。逆に、工場で大量の機械に囲まれ、大量生産に関わるときに、多くの人と協働していても孤立が生じるのである。
産業的生産は、教育を受けたこと、もしくは受けなかったこと、さらには拒絶したことによって人々を各種の労働に振り分ける。ここに現代的貧困が有効に働いている。高度な専門的知識を有しながら現代的貧困状態にあることは矛盾ではない。現代的貧困は、教育によってすべての人間に浸透しているのである。こうした状況では、各人がしうることの少なさが重宝される。つまり、自律的に活動し生きていくことができないがゆえに、「自分がしうることに、忠実に従うこと」によって、自分のしうることの少なさから解放され、生きることを許されるのである。また、「自分がしうることに忠実に従う」ところにだけ失敗というものが生じる。しかも倫理理的な価値を帯びて、ミスとして生じる。機械的なものと倫理的なもの結び付けるのがこのミスである。このミスを繰り返さないことが学ぶことの目的となるのだ。
しかし、これは「自分がしたことから学ぶ」といえるのだろうか?決してそうは言えないだろう。「自分がしたことから学ぶ」ことは、繰り返しによる改善を含まない。そこには反復による「卓越」があるのだ。それは自己の手段化はまったく存在せず、自己からの逸脱だけが存在するのである。その過程には、一切誰の目も生じてこない。完全なる自律的行為である。逆に、改善には多くの目が生じる。そしてそこに見られる私なるものが生じるのである。しかも、その目を私は見返すことができない。ただ一方的に見てくる眼に囲まれるにである。その眼は商品や生産機械の中にも宿る。機能上の正常性、見ための正常性、などといったあらゆる規格というレンズを通して、生産を行う私を見てくるのだ。その結果、機能や形、味などの目に見えるところの外側にだけ、私の自由、ミスのない自由、ミスが問題とならない自由が存在しうることになる。それは一つの商品が私のものではないことを意味している。それは二重に私のものではない。それは当然資本的にそうであり、消費者の目の見えないところで、手を抜き、ミスを隠した商品であるからそうである。分業化され、機械化された労働であるがゆえに、私が商品から疎外されているというのは巨視的に見た学術的言説にすぎない。正確には、自分が作ったものが、誰にどのように使われるかわからないこと。その商品が消費者にどのように使用され、長期的に見てどのような効果を産むかが分からないこと。商品をつくる過程に生じる環境破壊に目を向ける余地のないこと。さらには、商品の原材料を選定しておらず、規格通りに生産することしか許されていないがゆえに商品から疎外されているのである。
職人が巧みな技術を習得し、商品の見えるところと見えざるところ、つまり表裏を超越する丁寧な仕事をすることは可能であり、多くのものに眼を凝らす、つまりその主人となって見返すことは可能であり、そうした優れた職人は実際に存在する。しかしそうした人も、計画された設計や規格化された材料や部品の選定から自由にはなれない。そうしたものから一歩も外に出ないことによって職を繋ぐことが可能となっている。つまり、優れた職人もまた市場に依存し、収入によって生きているのである。それが悪いと言っているのではない。こうした、専門性、熟練性、規格化された生産の尺度だけに、人間の生産が閉じ込められていることに問題があるのである。こうした現代の尺度が存在する限り、現代的貧困は、金銭という唯一の尺度による貧富を産み出し続ける。
こうして生産された商品やサービスを消費するのも私たちである。機能や形状、味といった見えるものだけに依存する限り、その裏で進行する環境汚染や人体被害は不透明でありつづける。使用方法を決定づけられ、商品と商品が使用者による選択ではなく、規格化され、パッケージ化され結び付き合っているそのままに、使用する単なる消費者に私たちはなりさがっている。これも現代的貧困を産む。大量の商品やサービスに囲まれていても、常に欲求不満の状態が作られる。こうして、生産の生産、消費の生産は円環上になって一つの流れを産み出しつづけるのだ。要求するものが生産されるのではなく、提供されたものがあたかも要求されていたかのように存在するのが現代の貧困の極致である。これは、ドゥルーズの社会的服従で説明されることである。この現代的貧困、社会的服従の円環から抜け出る方法とは、「自分がしたことから学び」「自分がしたことで生きる」という、小さな円環を各人が作り出すことによるだろう。「働くために学び」「生きるために働く」という円環から抜け出し、大量生産、大量消費の円環からも抜け出すのだ。
イリイチは序章を以下のように締めくくっている。
「ある種の幻想を暴露し、市場依存を永続化させる専門家の権力を粉砕するある種の戦略を提案する」
私は、この書によって展開されるイリイチの提案を、詳しく読んで日々の生活の中で実践していきたい。彼が提案するのは、ラディカルな自給自足の提案ではない。現代的自給と呼ばれるものらしい。この現代的自給を、私は私がしたことから学びたいのである。
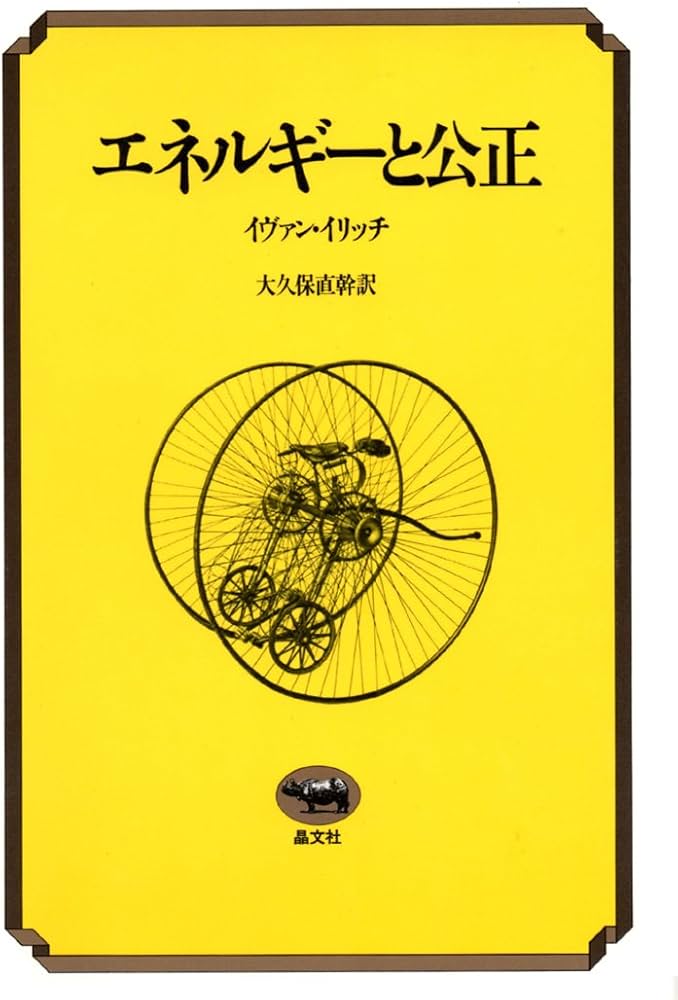
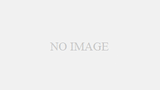
コメント