『千のプラトー』において、ドゥルーズは「機械状隷属」と「社会的服従」の区別を説明している。
隷属とは、人間が自己の主体性を失い、他の人間や技術的機械、道具と共に同じ構成部品の一部となって協働することである。上位コードの管理下に置かれ、歯車となって、これは全然比喩でなく機械の一部になっている状態である。
社会的服従とは、人間が自己の主体性を放棄せず、自らの外部の対象、他の人間や技術的機械、道具を主体的に使用する状態である。では、なぜそれが服従とされるのかというと、ある中心的な役割を担う外部の対象と関係を持たない限り、もはや生活がなりゆかず、それに必然的に依存せざるを得ない状況に置かれていることにある。こうした状況をを、イリイチは「根源的独占」と呼んでいる。スマートフォンがなくてもガラケーがあれば、こと足りるという状況であれば根源的独占ではない。しかし、スマートフォンがなければ、他人と連絡することも、どこかへ入ることも、何かを購入することさえできないといったように、他の外部対象と繋がることを不可能にすることによって、その対象に依存せざるをえない状況に置くのである。もちろん、スマートフォンがなくては購入できないものは、スマートフォンがなければ必要とさえ思わないものなのである。しかし、それがなければ、社会的恩恵を受けられないように思われることが社会的服従を強固なものにしている。スマートフォンや車、マイナンバーカードに至るまで、所有は任意であり、使用者となるか拒否するかということに関しては自由であるが、それを所有しなければ、生活が成り立たなくなるような不安に駆られるという点では共通しており、その使用者になっている。それらが網目状に繋がりあうことによってによって、私たちは自らは自由な使用者のまま、そうした網目状システムの管理を強化することに参加している。網目状システムは私の身体の外の空間に限られたものではない。私たちの欲望は、車の所有-ショッピングモールでの買い物を繋ぎ合わせている。また、スマートフォンはSNSを介しーディズニーランドやUSJと繋がりあい、遊園地とショッピングモールは併設さえして、横糸と縦糸を紡ぐかのように網目状に配置されている。高速道路は、網目状のシステムの上をショッピングモールから遊園地へと走る、それ自体が網目状の構造である。上位のコードは、こうした中心を担う機械を通して、欲望を操作することによって容易に管理を行い、かつ相互に監視しあう状況をつくりだしている。
以上のことから、社会的機械は人間の主体性を尊重する。そのため抑圧を手段として使わない。がゆえに、抑圧よりもより巧妙な手段によって服従を作り出しているのである。服従は隠されており、苦痛を伴わず、服従していることにさえ気づかない。もしそれが服従されているのだと聞かされると、怒りさえもするだろう。「だから何だよ。」と。かつて服従が見えていたころ、自発的服従という言葉があった。それは、主体性の判断によって、対抗行為を自ら取り下げることを意味していた。自己の主体性を抑圧する対象が私たちにはまだわかったのだ。だが現在の社会的服従は、抵抗するものがもはや見えない。ゆえに抵抗する必要を感じない。対抗行為はは抑圧するものへの抵抗から、迷惑をかけてくるもの、足を引っ張るものへの抵抗へと形を変えさせられたのである。
とはいえ、現代においても服従と隷属は共存している。それは労働と余暇である。さらには、その労働の内部においても、厳しいノルマと監視により主体性が丸裸になるような精神的苦痛を伴いながら仕事をするくらいなら、完全に主体性を放棄し、生産設備の一部となって働くことに少なからず自由を感じることは確かである。しかし、そうした自由が限定された場においてであることは明らかであり、結局は、余暇へとより強固に繋ぎ合わされていのである。
こうした隷従と服従は国家というメガマシーンの中で、正常とみなされている。労働とはなによりもまずストックを産むことであり、生きるためのものではないにも関わらず。ストックとは自分自身のストックではない。国民となるには、自分が生きるために自由活動をするのではなく、明日、明後日へと自己を再生産するだけではなく、ストックという余剰を産み出すことによって認められ、保証を受ける対象となるのである。
これまで述べてきたことが、条里空間における私たちの現実の生である。
しかしこれとは別の生がある。それは残酷さを条件とする生である。つまり、余剰を享受できないがゆえに、切り捨てられることもある生である。姥捨て山に抱く恐ろしさとは、条里空間側から見た別の生である。これが平滑空間である。平滑空間における生は、ストックをもたず、保険をもたず、財産の所有がないがゆえに、労働を必要としない。働くことは生きるためではなく、働くことが生きることなのである。雇われることがないがゆえに、余剰を産む必要がない。条里空間から見れば、「怠惰の権利」と呼ばれるものであり、両者の中間においては「創造的失業」と呼んでよいと思う。しかし、平滑空間への移行が、より辛い生を耐える必要を伴う場合も多くあるであろう。中世において、駆け込み寺が自由空間であり、縁切り寺と呼ばれ、権力から自由でありえたのは、より厳格な内部の規律を見過ごしてはいけないだろう。
私たちは条里空間の側から自給自足を夢見ているだけではいけないだろう。自給自足とは条里空間に囚われたものが抱く幻想にすぎないのかもしれない。そうした幻想を抱きつつ、いつの間にか日々は過ぎ、老害と呼ばれ、孤独死を迎えるかもしれない。条里空間からみればまさにその通りの生を終えようとも、平滑空間へと移行することによって、その生は意味を変える。老いと死の不安を払いのける条里空間、他者の老いを迷惑とする条里空間から、平滑空間へと移行し、自らを連続変化させなければならない。なぜならばそうした不安を払いのけようとするときに他なるものが迷惑として介入することがもはや平滑空間には存在しない。平滑空間は、他者に侵入されても即害を被るような場所ではない。存在することによってそこを占め、居場所となる。そうした平滑空間へと自己を連続変化させるために、まず何をすべきなのだろうか。


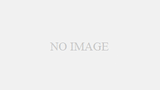
コメント