不満を表すこと。私たちはそれを求めているのだろうか?わからない。また、不満が言えないから、不満をためるのか、それもわからない。不満を言い合えることが大切なのか、それもわからない。そして、そもそも不満は誰が言っているのだろうか?言わされているのではないか?不満を言うことによって、居場所が開示され、初めて私がそこに立って存在するようになるのではないか?
ただ言えることは、不満を表すことができない場所があること。そして、その区画は肌感覚にも増えている気がすること。それにもかかわらず不満を表す人が増えていることである。
不満を表すこと、不満を表わさないことの二項対立は根本ではない。不満を表すことができる、さらにはそれを我慢するのは、すでにそこに居場所があるからのなのである。居場所のないところに、この対立は生じえない。ゆえに、これらの表現は居場所の中で起こるのだ。ゆえに、この表現の葛藤のより根本には、居場所と非居場所の対立が存在する。非居場所の中では、不満や怒りがあったとしても、それを表現することは不可能である。この非居場所は産業主義的資本主義の社会の中で巧妙に区画整備され続けてきた。治安の悪い地帯のコンビニや技能実習労働などで働いている外国人労働者がそれを如実に見せている。彼らは不満を表す居場所をもたない。不満を表せる居場所とは強制的に帰国させられる母国なのである。また、最近では介護職にも外国人労働者が雇用されている。これは、別のところで論じたいが、介護を受ける老人の怒りにさらされる外国人労働者の居場所と非居場所の問題。言語や文化を異にするということが、介護を受ける老人側の怒りを表現できない状態を作り出すように区画整備されていること。これらのことからも見て取れるように、不満や怒りは、この居場所と非居場所の区画整備の上で生じている。
彼らほどでなくとも、産業主義的資本主義にみられる区画整備は、チェーン店に代表されるが、そればかりではなく多くの会社を飲み込むように、拡張されてきている。ゆえに、多くの人々が、職場の外に、また家庭の外に、第三の趣味などでつながれる居場所探しが大切だとされるようにもなってきている。職場、家庭、第三の居場所、これらを仕切る頑強な壁、そして区画整備。しかし、同時に見えてきたことがある、それは、産業主義的資本主義社会が、特にサービス提供においてこれらの壁を必要としていること。店員にとって不満を言えない居場所が、同時に客にとって不満や怒りを表すことのできる唯一の居場所になっていること。そして、このことが、産業の成長にってガソリンの役割をしている。やすらぎや癒しを提供するサービスが、癒し空間の壁の外の、非居場所の存在を前提として成り立っている。サービスが過剰になればその壁の外と内の隔たりは大きくなり、壁は強固に分厚くなる。そして、癒し空間の中にさえ、客と店員という、居場所と非居場所の区画が生じることになる。「お客様は神様です」というところの神様とは居場所を求めるクレーマーのことなのである。この神様は、自分が存在する場所=居場所とすることができない。
以上のことを述べたうえで、コンヴィヴィアルな社会を目指すことには何ができるのか?それは、居場所と非居場所の壁を壊すのではなく、穴をあけることである。定められ、求められた行動しかできない場所の中で、予想に反した行動ができる余地を作り出すことである。その穴を通して他者と繋がることである。壁が隔てる空間の両側の異質さを弛緩させることである。その方法とは、他者との関係を閉ざさない空間の中に身体を中心とした不満をいうことができない非居場所をつくることである。
重松清の『ナイフ』で、主人公はナイフを隠し持ち、居場所と非居場所の境界に立ったといえるのではないか。ナイフは決して人に向けられたものではない。ナイフが切り裂いたのは居場所と非居場所の境界ではなかろうか。さらには、工具を手にすること、楽器を手にすること。これらに共通するのは、あらかじめ、使い方や遊び方が定められた家電製品やゲーム、サービスを利用するのではないところである。これらの、道具は卓越と関係している。卓越とは、非居場所と居場所の境界を越え続けることである。卓越はどこまでも居場所を拡張し続ける区画整備とは無関係である。卓越は身体とともにあり、疲労や老いなどの体力の限界によって限界づけられている。行動速度や食べきれるものなどなど。しかし、この卓越における限界が満足を生むのである。これが足るを知るということである。ギターを手にし、弦をつま弾くだけで、そこに居場所が生まれる。しかし、他の楽器とアンサンブルするとき、先ほどまでの居場所は突如として非居場所となる。自分の好きなようにポロンとつま弾くことによって生じた居場所は非居場所に乗っ取られたのである。ゆえに、アンサンブルの中にもう一度、居場所を見つけ出さなくてはいけない。それは、自分だけの居場所ではなく。他の楽器が入り込むことのできる穴であり、つまりリズムである。これが卓越であり、職人が工具を手にし、制作物と対峙するときにも同じことが言える。
職場、家庭、第三の居場所等の区画整備を拒絶し、それぞれの壁に穴をあけ、互いを緩くつなぎ合わせる。そのためには、コンヴィヴィアリティーのための道具が必要であり、そのつながりが機械状のアレンジメントを形成する。産業主義的資本主義における職場、家庭、第三の居場所等は、誰かが作り出したものである。現代人はその中を忙しなく移り行くのが普通だと考えている。それは間違いである。その考えを持つかぎり、非居場所を前提とした居場所づくりのサービスの拡張整備を止めることはできない。なすべきことは、その逆転である。移動するのは各人の身体ではない。各人がその身体を中心として、職場、家庭、第三の居場所等と繋がるべきなのである。そして、それらをごちゃまぜにし、アレンジする。卓越というのは混ぜ合わせることでもある。不満を言うことができないのは、もはや言えないからではない。責任を伴う非居場所の到来と居場所の探求を不断に繰り返すこと。到達や達成は存在せず。非居場所の到来に対する卓越だけが存在する。しかし、この意味における非居場所とは居場所と対立するものではない。居場所は区画整備されたものではない。非居場所とは世界のことである。

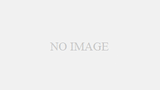
コメント