権力装置の一つとしての学校教育は、教師の命令に従わないものを落伍者とし、工場労働へと繋げる。落伍者は、自らを落ちこぼれと自認することによって、あきらめて工場への道を歩む。学校教育が落伍者をつくることを一つの役割としていることに間違いはない。しかし、それが中心の役割ではない。また同時に、学業に優れたものに情報を伝えるために学校教育があるのでもない。塾に通う学生がこんなにも多いことからも明らかである。落伍者でも、学業に秀でた者でもなく、学校教育がその目的の中心に据え、作り出そうとしている優秀者とはいった何なのであろうか。
それは「教師の命令に従っているように振る舞う学生」であろう。これが学校教育の優秀者なのである。正確には「教師の命令に、教師がいる前で、従っているように振る舞う学生」である。教師と生徒の間に、師弟関係があるならば、つまり教師の権威がありさえすれば、教師の命令は、教師の目、命令に従うかどうかを監視する目は不要となるだろう。しかし、学校教育は教師の目を前提とすることによって成り立っているのである。教師の言葉は、命令も含め、それは彼自身の言葉ではなく、つまり彼が経験したことを伝えるのではなく、それは伝達でしかないのだ。社会的要請(=コード)の伝達。こうあるべきだということの伝達。教師は、監視の目を持つことによって、もはや自分の言葉を捨てているのだ。言葉を信じていないとさえいえるのではないか。自らの言葉の使用を限定することによって、学生の可能性を限定するというのが正確であろう。
教師の目を前提とする学校教育の中で、教師の目を盗むことや、教師の目のないところでサボることは、教師の目の前で従っているように振る舞うことと矛盾するどころか、従っているように振る舞うことの条件でさえあるのだ。そして、こうした狡猾ともいえる学生こそが産業主義的工場労働を将来的に担う優秀者なのである。教師の目は工場長の目へと引き継がれ、その目のあるところで、必死に働くことへと潤滑に繋がるからだ。工場には工場長以外にも監視の目は無数にある。機械の駆動速度、反復間隔や生産数、これらも一つの目なのである。こうした監視の目のないところで、悪口を言ったり、手を抜いたりすること、これは工場労働でしか働けないという点でも優秀者の条件といえる。
監視の目の外で手を抜くことは、彼らの反抗であるが、それは所詮、怒りや反抗の強度を自ら低下させる空気抜きのようなものであり、工場労働においては、重宝さえされるのである。話は外れるが、ネットニュースなどで、自己と同調的な政治批判の記事を見ることも、反抗の強度を低下させるのに役立っていることを見逃してはいけない。
このように、優秀な元生徒は工場労働において、役職をあたえられるだろう。それは、監視の目に疎く、左右されない者、つまりは学校教育においては非優秀者に当たるものと対立するだろう。監視の目に左右されない者は、マイペースに働き続ける。監視の目の前だけ必死に働く者をよく思わず、自然と対立する。この対立こそが、新たな監視の目となるのだ。同僚同士の相互監視。監視の目の増殖。この対立、新たな監視の目は、工場の管理体制を強化することになり、相対的に労働者を弱くする。元優秀者は、より監視の目の前で従順となり、監視の目に疎いものは、より監視の目を無視するように黙々と働くか、より高次の監視の目に、不平を告げるようになるだろう。監視の目は、優秀者により良い地位を、そして非優秀者とは友情を結ぶ。
「一緒にサボること」、それは字義通り監視の目を盗み、仲間内でサボることである。しかし、同時に抜きん出ようとする者、マイペースに行動する者を露見させようとする行為でもある。サボるということは、学校においても工場においても禁止されているように思われる。しかし、それは先ほど見たように、学校教育においても工場においても全く異常なことではないのだ。建て前上は異常でありつづけながら普通なこととして存在している。これが学校教育が秘密裏に成し遂げていることである。教師の前で従っているように振る舞い、教師の目を盗んでサボる。これこそがまさに学校教育において普通とされるものなのだ。推奨されていることなのだ。一緒にサボることは、普通と異常に線を引き、異常と普通を逆転させる。一緒にサボらない普通の者が突如異常者に仕立て挙げられたりもする。異常者にしたてあげられたものを仲間から排除しようとすことも起こりうる。排除から逃れるために、または、監視の目のないところでサボる者にたいして、対抗するために自分もまたサボるとき、罠にはめられるのである。また、サボるものに対抗して、より必死になにかをなす場合もまた罠にはめられるのである。一緒にサボることなど不可能である。「一緒にサボること」、これは学校で学び、社会で使用される排除の条件である。誘われてサボることも、サボっている人を見てサボることも、どちらもしてはいけない。自分自身のサボりを見出す必要がある。そのサボりが、必死に働くことを手段とするのなら、それは罠にはまっているわけではない。その時、違った方法によって、一緒にサボることも可能となるのである。もちろん対抗心を失うことなく。
私たちは、新たな学生(=学び生きるもの)とならなくてはならない。学校教育への郷愁、後悔を忘却し、自らしたことから学び、従うべき人と出会い、友情を結ぶ。学校教育が、従うことと友情を大切にするのとは別の仕方で、学生となるのだ。

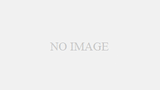
コメント