国家と同僚、どちらも身近な存在でありながら、それらと関係を断つこと。こうした関係を絶った共存、それが可能ならばそれはひとつの勝利となるであろう。
上からの指示を伝えない、何かを隠すこと、様々な失敗を助長させる圧力によって、個人同士の関係に留まらない迷惑行為を生じさせようとして、関係してくる。逆に、誰かが悲しむと言って、良心に訴えることによって、関係してくる。また、どちらを選択するかは自由だが、意に反した方を選べば不利益を被る選択を課すことによって、関係してくる。これは、究極的には、安楽死の法制化に行き着くことになる。楽に死ぬ方法があるのに、それを選ばないということは、苦しんで生きるのは当然だという空気を作り出すことになる。人は老いによって死ぬのではなく、老いの排除によって死ぬことになる。これはドゥルーズの言う非身体的変形である。さらには、危険性(建物や街路樹の倒壊のおそれ)を理由として、関係してくる。こうした関係は、どれも排除の関係を示している。各人同士の関係と社会全体に及ぶ関係は、明確に切り離せず、両者は補完関係によって、排除の関係を構造化している。
こうした関係を築く際に、ダブルバインドが利用されることがある。ゆっくり仕事をすれば良い、(しかし1秒でも遅れたならば絶対に許さない。)好きに犬を飼えば良い、(しかし、その犬は屋外で飼える犬でないと許さない。)マイナンバーカードを登録しなくても良い。ワクチンを打たなくても良い。同僚の言葉、家族の言葉、国家の言葉、発せられる言葉は、どれも、自由を与えるようで、私たちを自らの意思で管理の中へと進んで入り込ませようとする。
関係を断とうとするもの、つまり自律して関係に従わないものは、関係に従えないものよりも憎悪を被る。排除には二通りあることがわかる。従えないものに対する、やましさのない排除。従わないものに対する、憎悪を浴びせたり、不利益を被らせる排除。第三者、それが神であったり、暴力装置であったりするのだが、ばちや罰を受けさせることを願うのも、従わないものに対する排除の関係である。
しかし、排除の関係を保持しようとするものよりも、関係を断つことにしか興味の無い者のほうに優位性があると言えないだろうか。
あたかも排除するものが従わせようとするその関係に、進んで飛び込むこと。しかし、それが望むこととは全く異なる方法の創造によって従う。さらには、排除されているかのように自律する。それは従っているかのようにして、抵抗することである。
黙々と働くこと。嫌がらせを受けたら、その分より黙々と働く。道具を隠されたら、より良い道具を自腹で買うこと。決してより地位の高いものに、助けを乞うたり、すがろうとせず。
子供を産めと言ったら、産もうとする。
食料自給率を上げろと言ったら、食料自給率を上げる。
納税しろと言ったら、より多く納税できるように働く。
70歳まで働けと言ったら、それ以上まで働く。
SDGsが大事と言ったら、SDGsを達成する。
祖国を守れと言ったら、進んで祖国を守る。
言葉の裏には、私たちを管理し、思い描いたように行為させようとする、思惑がある。
言葉とは、情報を送るためではなく、従わせるためにあるのだ。正しくは、従っているかのように振る舞うことを強制するためにあるのだ。その言葉が、目標の達成に、責任を持っていないことは明らかである。そうした言葉の中で、自己の輪郭を固定化し、形成してはいけない。ゆえに、私たちはそうした言葉によって思い描かれる行為とは全く違った方法で、その言葉に従わなければならない。
言葉に従っているかのように振る舞えば良いのだ。重要なのは、従っているということに、常に意識することだ。それは従うことに意識すること、言葉への隷従、受動性の真逆のことである。言葉を玩具のように扱うのである。解釈するのではなく。
それは、自分が多数派の中で生きていくことの否定ではなく。絶えず少数派へと、絶えず創造を絶やさず、人生を自分のものとして生きていくことである。多数派から少数派への生成変化とはこのようになされるのではなかろうか。決して、多数派の外で生きることだけが関係を断つことではないのだ。少数派は、多数派の中でこそ、生きていくのだ。
ダブルバインドを破壊することによって、創造を解き放つ。責任は常に自分の中にある。これが、関係を断つ共存の方法ではなかろうか。
イリイチの言う、現代的自給
ドゥルーズの言う、自律、少数派、スタイル
などの概念も、上述したことと、多少なりとも関連がありそうである。
私の手はまだまだ私の器官である。ゆえにギターを手にする。ゆえにペンを手にする。ゆえに鑿を手にする。ゆえに鍬を手にする。ゆえに槍を手にする。銃さえ手にするかもしれない。しかし、それを誰かの号令によって発射してはいけない。


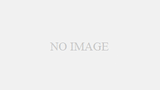
コメント