ベルクソンは、第一章における考察のまとめとして、知覚を以下のように図式化している。
「知覚においては、次々と絶えることのない瞬間的ヴィジョンを記憶力の連続的な糸で繋いでいくことに限られ、それらのヴィジョン自体はわれわれのほうではなく、むしろ事物の部分をなしている、ということになるはずだ。」
この事物の部分をなしているヴィジョン自体こそが純粋知覚である。
記憶に頼ることのない純粋知覚は、意識に表象=イマージュを与える役割を担っているのではなく、物質=イマージュと共にあり、物質のもつある側面、それに対して身体が行為可能な側面と直に関係する。ゆえに純粋知覚は、神経系や脳の中には存在せず、知覚対象が現前する場所に存在し、イマージュと関係する。イマージュとの関係の多様性は、身体がもつ神経系の複雑性によるものである。
「物質のうちには、現に与えられているより多くのものはあっても、それとは何か別のものがあるわけではない、と。確かに、意識的知覚は物質の全体には到達していない。意識的なものであるかぎり、知覚とは、その物質のうちでわれわれのさまざまな欲求に関係するところだけを分離ないし「分別」することにほかならないからだ。だが、物質の知覚と物質そのもののあいだにあるのは、単に程度の差異であって、本性の差異ではない。純粋知覚と物質は、部分と全体の関係にあるからだ。これはつまり、物質はわれわれが現にそこに見て取っているのとは別の種類の力を及ぼしたりはしない、ということである。」
われわれの知覚は、権利上は物質そのものを知覚しうる。なぜならば、純粋知覚とは物質そのものの中に身を置くことだからだ。もちろん、物質そのものを全て知覚することができないのも上述の通りである。私たちの知覚を構成する身体の神経系が完全ではないこと、そして、それらが完全なものに近づいたとしても、純粋知覚とは結局のところ物質とともに物質を構成しているのであり、物質から知覚を切り離すことによって、物質を知覚の中に完全に包摂するようなことは不可能である。これらのことから、先ほどのベルクソンの引用部分にもある重要なことが導き出せる。それは、純粋知覚は物質そのものと一致することは事実上不可能であるが、それらの間にあるのは程度の差異であって、本性の差異ではないということである。
このことを前提として、ベルクソンは記憶についての考察を始める。
常識においては、知覚は記憶力の力を借りて瞬間的なヴィジョンを連続的な糸で繋ぎ合わせる、とされる。しかし、純粋知覚においては、知覚はイマージュがあるところに存在するとされた。これらのことから以下の問いが生まれる。イマージュはそれがあるところに知覚されるにも関わらず、われわれの主観の中で知覚されるように思われるのはなぜだろうか?
ここでもまた、「科学のシステム」と「意識のシステム」の共存を見ていく必要がある。
すぐにわかることだが、「意識のシステム」を形成しているのが何よりもまず記憶力である。この意味での記憶力を知覚に組み入れ直すことがベルクソンの記憶に関する最初の取り組みであり、イマージュはそれが知覚されるところにあるにも関わらず、われわれの主観の中にあるように思われるということの理解への足掛かりとなる。
まず、記憶力が瞬間的なヴィジョンをを繋ぎ合わせるという、粗雑な定義に修正を加えなければならない。われわれの意識において、瞬間なるものは、知覚を構成する最小の時間単位ではない。なぜならば、知覚の変化を感じるためには、変化する前の状態と変化後の状態を同時に知覚しないかぎり、変化した瞬間を捉えることはできない。ゆえに、変化の瞬間と呼ぶものすら、記憶力の働きによって変化前と変化後の状態が一つの知覚へと繋ぎあわされているのである。音楽も、ある瞬間の音の中に、曲の始まりからそこに至るまでのすべての音が凝縮されていないかぎり、メロディーの美しさは感じられないだろう。このように、変化するものの知覚、さらには音楽のように持続するものの知覚においても、記憶力がその根底で働いているのである。
「記憶力は実際上は知覚と切り離せないもので、この記憶力は過去を現在のうちに割り込ませてくるのと合わせて、持続の多数の瞬間をただひとつの直観に凝縮もしている。この二重の作用によって、記憶力は、権利上ではわれわれは物質を物質のうちで知覚しているのに、事実上はそれをわれわれのうちで知覚するということの原因になっているのである。」
これらのことから、われわれの知覚はそれ自体一定の厚みを持っていることが言える。この厚みを帯びた知覚を無限に分割することによって、意識のシステムから科学のシステムへと移行することはできない。それは時間を空間化することであり、確かに本来拡がりを持たないものを拡がりのうちへ移すことであるが、意識のシステムのうちにおける抽象化に過ぎないのである。この抽象化から時間を無限に分割するという考えが生じ、その結果、瞬間なるものも生まれるわけだ。しかし、この意味での瞬間が知覚を構成することはない。知覚における厚みとはゆえに空間的な広がりではないのであり、記憶力がつなぎ合わせたものが、空間上に拡がりをもって現れることはないのである。科学のシステムへの移行ができるとするならば、それは根源的に意識の中から記憶力を排除するしかないだろう。そうすることによって、権利上は純粋知覚はつまり物質そのものの中にみを置くことができるであろう。
これらのことから、われわれの知覚は、記憶力の介入する程度によって、物質があるががままに、それがあるところに知覚しうるし、またその逆で、われわれの意識の中で知覚されるようにもなるのだ。
記憶力によって、過去を現在のうちに割り込ませることによって、現在の経験を、過去に得た経験によってより豊かに知覚することが可能になる。それは、物質そのものをあるがままにより豊かに知覚することを可能にするだろう。しかし同時に、矛盾するようだが決して矛盾ではなく、よりその物質を意識の中で知覚するとも言えるのだ。
「われわれが未来に手がかりをもつには、それと対応して同じだけ過去への振り返りが必要であって、前に向かうわれわれの活動力の推力は自分の背後にさまざまな記憶がなだれ込めるための隙間を作るのだ。かくして、記憶力とは、われわれの意志の非決定性の、認識の領野における反響なのである。」
この非決定性が記憶によって豊かになることが、われわれの行為可能性をより広げ、イマージュの知覚をも同時に豊かにする。そしてこのことからベルクソンが導き出したのは、
「純粋知覚は物質の全体、あるいは少なくとも物質の本質をわれわれに与えているからには、そしてそれ以外は記憶力に由来しつつ物質に追加されるものであるからには、記憶力は、原理上、物質からは完全に独立した一つの能力でなければならない。したがって、精神が実在であるならば、まだにここ、つまり記憶力の現象においてこそ、われわれはそれに実験的に触れるはずだ。」
以上のことから、記憶力が物質から独立した力能であるならば純粋記憶とは、どこにあるのかという問いが生まれる。これについては第二章にて考察される。
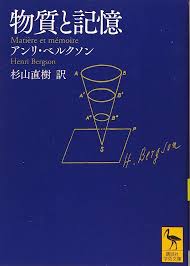


コメント