ベルクソンは、情感という語を身体内部に位置付けられる諸感覚の意味で使う。表象が対象の側に属する緒状態を示すのに対し、情感は身体表面ないし内部の状態を指す。情感は身体内部の物質的状態の知覚から生じ、怒りや喜びといった非物質的とされる感情とはひとまず異なるものとして使用される。その例は、痛みや痒み、喉の渇きや空腹感、疲労や眠気などである。さらに、運動感覚も情感の一つである。身体バランスを保つ運動感覚は、潜在的可能行為を素描する知覚と、現実に遂行さる行為のあいだで、不断になされている。歩行などにおいて、この情感を伴わずとも無意識の自動運動として遂行可能である。しかし、ひとたび地面が不安定な道にさしかかると、この身体バランスを保つための運動感覚=情感に意識を向けることになる。また、身体的躊躇も情感の一種である。日本人ならば、ひとたび土足で畳の上にあがろうものなら、歩き方を忘れたように、ぎこちなくしか脚を出すことができないだろう。
我々の知覚は、イマージュの総体へと不断に身体の可能的潜在的行為を投影しつつ、その過程で、あるイマージュから、そのイマージュに対して行為可能な側面を取り出すのであった。ゆえに、あるイマージュが非物質的なものとされる意識に表象化され、その中でこれまた非物質的な情感を刺激して、それがまた非物質的な欲求となり、延長の中で生じる物質的な行為へと還ってくるのではないことは明らかである。情感は、神経系の中心たる意識中枢なるものが生じさせる非物質的な表象を介して生じるのではない。神経系に中心があったとしても、それはどこまでも物質的であり、それは潜在的可能行為の伝達の中心を示すだけであり、意識をその中に生じさせる容器のようなものでは決してない。
情感は、イマージュの総体の中に直にある身体というイマージュの内部の神経系に、身体外部または身体内部からの刺激によって起こる興奮状態なのである。
低級の生物であると、可能的潜在的行為と現実行為の間にある非決定性が僅かであるため、現実行為の反響としての情感がほとんどを占める。しかし我々は、非決定性の領域が多い分、現実行為に伴う情感のほかに、現実的行為の遂行しなくとも可能的潜在的行為をイマージュに投影することだけでも情感を受け取ることができる。ゆえに、疲労を例に取り上げるならば、疲労とは現実行為の結果による肉体的疲労であると同時に、可能的潜在的行為をあるイマージュに対して働きかけることができないことによるのだ。労働で疲れた夜、ベッドに横たわり本を読もうとしても、文字に焦点が合わず視線が浮遊する経験などがある。これはまさしく疲労という情感であり、潜在的可能的行為を本に書かれた文字のイマージュに投影できないことによるのだ。疲労が非物質的な意識の中に生じる感情でないことはこのように明らかである。
可能的潜在的行為と現実行為の隔たりは、自由の大きさの尺度であり、それを外から見るならば意志を持っていることになる。この隔たりを、隔たりのまま埋めることができない場合に、より内面的な感情としての不安や絶望も生じるのである。そう考えるならば、疲労とはこの隔たりを一時的に、隔たりのままにしておく状態ということができるであろう。言い換えるならば、隔たりが隔たりのまま、隔たりを喪失したということが言えるのかもしれない。疲労がそれ自体、不安や絶望を産まないのもこの一時的中断ということが前提とされているからなのだろう。これらの考察からも、可能的潜在的行為と現実行為の隔たりが不安や絶望というより内面的な感情を引き起こすことは否定できない。しかしここではそれらの説明を避け、精神の台座としての身体というより客観的なものに焦点を当てる。つまり、可能的潜在的行為と現実行為の隔たりが失われるところにおける情感を見ていくことになる。
「知覚は、われわれのように理解するかぎり、事物に対するわれわれの可能的行為を示す尺度であり、したがって逆に言えば、われわれに対する事物の側からの尺度であもある。身体の行為能力が大きくなるほど(それは神経系のより高度な複雑化に示される)、知覚が包み込む範囲もいっそう広大なものになる。だから、われわれの身体をある知覚対象から隔てている距離とは、まさしく、ある危険の切迫度の大小や、ある期待が実現する時までの遠近を示す尺度なのである。したがって、身体とは別の一対象、身体から一定の隔たりで切り離されている対象の知覚は、潜在的行為以外のものを決して示さない。だが、その対象とわれわれの身体との距離が減少するにつれて、ということは言い換えると、危険がより切迫したものになったり、期待がいっそう目前のものになったりするのに比例して、潜在的行為はますます現実的行為に変じようとする。では、限界まで進んで、距離がゼロになった、すなわち知覚すべき対象がわれわれの身体に一致した、つまりはわれわれ自身の身体が知覚すべき対象になった、と仮定してみよう。このとき、そのまったく特別な知覚が表現するのは、もはや潜在行為ではなく、現実的行為となる。情感というのは、まさにこれなのだ。こうしたわけで、われわれの感覚と知覚の関係は、われわれの身体の現実行為と身体の可能的ないし潜在的な行為との関係に等しい。身体の潜在的行為は、身体以外の諸対象に関わるもので、それら対象の中のほうに描き示されるが、身体の現実行為のほうは、身体自身に関わるもので、それゆえに身体内部に描かれるのである。かくして結局、現実的行為も潜在的行為も、それらの差し向けられる点ないしそれらが発してくる点へとまさに立ち返されるのであって、われわれの身体によって外的なイマージュは身体周囲の空間へと反射され、現実的作用のほうは身体自身の実質内に引き止められる、という具合になるわけだ。まただからこそ、外と内が共有する境界でもあるところの身体の表面は、延長の中で唯一、知覚されると同時に感じられもする部分になっているのである。以上からしても、やはり私の知覚は私の身体の外にあり、私の情感は反対に私の身体の内にある、ということになる。外的対象は、私によって、対象自身が存在する場所に、私ではなく対象の中で知覚されるが、それと同様に、私の情感的状態は、それが生じている場所に、すなわち私の身体の特定のある一点において感じられる。物質界と呼ばれるイマージュの体系を考えてみよう。私の身体は、そこにあるイマージュの一つである。このイマージュの周囲には、表象が、すなわち身体というイマージュから他のイマージュに対しての可能な影響が配置される。そして、このイマージュの内部には、情感が、すなわち自分自身に対しての現実の努力が生じる。われわれの誰もがイマージュと感覚のあいだにおのずと当たり前に立てている差異とは、つまるところ、まさにこうしたものである。イマージュはわれわれの外に存在しているという場合、それは、イマージュはわれわれの身体の外にあるという意味である。また、感覚のことを内的状態だと言うのは、われわれの身体の中で生じている、と言う意味である。」
情感は、われわれの身体内部にあり、イマージュはわれわれの身体の外にあるというのは、前者が延長のない精神にあり、後者は身体の外にある物質内にあるということではない。そうすると、また本書の最初に逆戻りすることになる。そして、表象とものは対立を続け、身体はその中間に存在する不明瞭なものでありつづけるであろう。
身体は空間内の数学的な点のようなものではない。また、情感も精神なる非延長に生じるのでもない。そうではなく、身体は神秘的なものではなく、イマージュの総体の中にある特殊なイマージュにすぎない。身体が特殊というのは、われわれの最もそばにあり、われわれがイマージュの総体を知覚するときに、常にその中心に位置するからである。そして、情感はこの身体というイマージュの内部や表面に生じるのだ。
疲労を例にしてみたように、身体的疲労は、現実的行為の結果である。それはまさに身体の各部位に感覚されるのであり、決して精神の中で感じられるのではない。
さらには、精神疲労というものも、身体内の神経系が不調に陥り、思うように可能的潜在的行為を描けず、たとえそれが現実的行為になった場合でも、思ったように上手く行為できないことでしかない。精神疲労も結局は、仕事道具や勉強道具、仕事の同僚や学校の人間関係の中で、上手く行為できないことなのである。常識も精神疲労という概念をノイローゼのようなものとしてこのよう使用している。よって、精神疲労はどこにあるのかと問われれば、行為がなされるその場所ということが言える。可能的潜在的行為の素描と現実的行為の遂行が繰り返される中で、逐一それが中断させられ、現実的行為の結果が自己や他者によって評価される、まさにその場所に起こるのである。
逆に、集中して作業している時は、可能的潜在的行為の素描と現実的行為の遂行は不断に繰り返されるのだが、それを遮るものは何もなく、無意識の自動運動として持続される。ゆえに、集中した作業中においては、疲労は現実的行為の量や密度に比例するのだ。
しかし精神的疲労は、可能的潜在的行為と現実的行為の間にある非決定性という領域でおこるのであり、その両者の不一致を起こすことであり、その不一致を自己なり他者なりに目撃されるのである。ゆえに、それは非延長的な精神の中に起こる不調ように思われる。そして常識も先ほどとは別の考えを起こし、自己矛盾に陥るのだ。しかし、この精神疲労といえどもどこまでも物質的行為に関係づけられているのであり、行為がなされる仕事場や学校といった空間の中にはっきりと延長を持つのだ。
このことから次のことがわかる。情感は、現実的行為によって生じる。しかし、それだけではなく、可能的潜在的行為と現実的行為の複合によっても生じるのだ。それはつまり、情感というものが知覚に含まれ、外的物質のイマージュへと混入されていることを意味する。嫌いな仕事や苦手な人間といった趣向を情感と同じカテゴリーに置くのは、また難しい考察を必要とする。しかし、以下のことは言えるだろう。こうした趣向も、情感と同じように知覚に混入されているのである。嫌いな仕事や苦手な人間は、まず私に無機質な仕事や人間として知覚され、それが主観の中で好き嫌いといった趣向によって無機質な物質の表象に脚色され、そしてはじめて不快等の情感を抱くというのは、明らかに間違いだろう。そうではなく、われわれは、直に知覚しうるイマージュそのものに、情感や趣向を混入させ、それがある場所において知覚するのだ。ゆえに、イマージュの純粋性、ニュートラル性を取り戻すためには、真っ先に、情感や趣向を取り去らなければならない。しかしもう一度言うが、それが権利上可能だとしても、そうした情感や趣向がわれわれの主観の中にあるとするのは間違いである。逆に、外的対象の中にあると決めつけるのは独断論以外の何者でもない。趣向は確かに、情感のように身体内に位置付けることができないが、それは精神の中にあるのではなく、先にも述べた、意識のシステムと科学のシステムの関係のうちにあると言えるだろう。
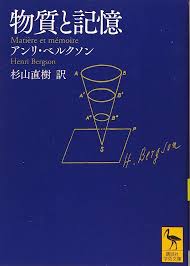
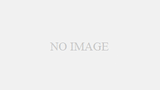

コメント