脳や脊椎、知覚器官を中心とした神経系の機能とは、刺激に対する表象を作成することではない。神経系の機能とは、刺激の受容とそれに対する運動装置を自らその一部となって構成することである。この機能だけを取り上げるならば、下等、高等な種別はおろか、ロボットとさえ本質的な差異を持たず、あるのはその複雑さ素材の違いである。特に重要になのは、神経系の機能が「連絡をつける」こと、あるいは「連絡を保留する」ことであり、その構造がどれだけ複雑になろうと、神経系は連絡の最中に刺激を表象に変えたり、刺激に何かを付け加えたりしないことである。
「高等な脊椎動物ともなれば、とりわけ脊椎に座をもつ純粋な自動運動と、脳の介入が必要な意思的活動との区別は、確かに根本的なものになる。だから、人は、受けた印象はこれまでのように運動へと花開くのではなく、今度は認識へと精神化するのだ、などと思い描いたりもするわけである。だが脳の構造を脊椎の構造と比べてみれば、脳の諸機構と脊椎神経系の反射活動のあいだにあるのは複雑さの差異だけであって本性上の差異ではないことは明らかである。」
神経系が数多くの運動装置を構成しているならば、ある刺激に対して、より多くの潜在的な可能行為を素描することができる。これは、下等な種に見られる接触のような知覚と運動(≡反射)が一体となっている運動装置に比べるならば、知覚と運動のあいだに必然性の鎖が緩んでいることを意味する。つまり、生物の側に委ねられる非決定性が増大することである。目の前に食物があって、それにすぐ食らいつくことを保留する運動装置が準備されているならば、それはより遠くの、より栄養価のあるある食物を食する可能性を持つことにもなり得るだろう。つまり、この行為の非決定性こそが、より遠く、より多くを知覚しうることの前提となるものなのである。非決定性をもつ生物を、その外から見るならば、その生物は意識を持っているように思われるだろう。ゆえに、このどこまでも物質的な構成をなす神経系自体が、一見、非物質的な意識を構成していると言えるのである。それゆえ、記憶を介さない純粋知覚とは、知覚対象の諸イマージュ、さらにはそれにつづく運動の諸イマージュと本性上の差異を持たないと言える。
意識的知覚が、知覚した「もの」とは異なる、脳内部に生じる「表象」を介して行為を選択するのではないことは明らかである。意識的知覚は、物質的な諸イマージュの中にあるゆえに空間的であり、同時に、身体という特殊なイマージュを中心とした行為の保留の中にあるゆえに時間的でもある。つまり、意識的知覚は、どこまでも必然的な物質的諸関係と、即座の行為の保留といった物質的必然性の鎖が弛緩する時間的なものとが交差する非決定地帯の只中に生じるのである。
「ある生物が自分の自由にできる独立分、あるいは生物の活動性を取り巻く非決定地帯と言ってもいいが、これは、その生物がどれほどの数の事物にどれほど遠くから関係できているのかをアプリオリに見積もらせてくれるものだ。この関係がなんであろうと、すなわち知覚の内的本性がどういったものであろうと、知覚の広さはそれに続く行為の非決定性の厳密な尺度になっている点は認められるのだから、そこから次の法則を述べることができる。行為が時間を自由にできるのと厳密に比例して、知覚は空間を自由にできる。
こうしてベルクソンは、人の複雑な神経系による非決定地帯を前提とし、意識的知覚の導出を具体的に行なっていく。ベルクソンは本書の冒頭で、イマージュを「もの」と「表象」の中間にある存在と定義した。それによって否定したのは、「もの」が物質界に属し、「表象」が意識界に属し、両者が神秘的な方法で交流しあうという考えだった。そのために、ベルクソンは、両者が分断される以前の物質界をイマージュの総体とした。そして、このイマージュの総体の内部で表象化が生じることを示すのである。ベルクソンは、「もの」も「表象」も存在せず、存在するのはイマージュだけだとする一元論を肯定するわけではない。ベルクソンが否定するのは、「もの」の外部、広がりを持たない精神なるものの内部で生じる「表象」を否定しているにすぎない。それゆえ、ベルクソン意識的知覚の導出は、イマージュの総体の中で、いかに表象化がなされるかといういうことになる。
あるひとつの存在イマージュに、何かが足し合わされることによって、表象イマージュ、つまり意識的知覚が生じるとするならば、その存在イマージュに何かが加えることによって、必然的にイマージュの総体を増大させることになるだろう。しかし、イマージュの総体の内部に存在する生物の神経系イマージュの中に、イマージュの総体を増大させる条件が加わっているはずがない。なぜならば、その生物の諸部分は取りも残さずイマージュの総体の中に組み込まれているからである。しかし、だからといって、イマージュの総体の外部にある精神なるものの中に意識的知覚を求めることは、本書では否定されている。そこで、ベルクソンは、存在のイマージュの表象化がイマージュの減少によって成り立つとする。
「表象への変換を得るために必要なのは、対象を照らすことではなく、逆にその一定の側面を暗くして、対象の大部分を差し引いてしまうことであり、それによってその残余部分が一つの事物として周囲を取り巻くものの中に埋め込まれたままになるのではなく、むしろそこから一幅の絵画のように浮かび上がるようにすることである。しかるに、生物は宇宙の中で「非決定性の中心」を構成しており、この非決定性の程度はそれぞれの生物がもつ諸機能の数と発達度に比例しているのだとすれば、生物が現に存在しているだけで、それは対象のうちで当の生物の諸機能が関心をもたない部分すべてを削除するのと同じことになりうると考えられる。生物は外からの作用のうち、自分にはどうでもよい部分を、いわば素通りさせるだろう。そして、それ以外のところは切り離され、この分離そのものによって「知覚」になることだろう。(…)そして、イマージュの作用のこうした減少分こそ、まさにわれれがイマージュについてもつ表象なのである。」
「現に存在しているイマージュ、客観的存在たるイマージュが表象されたイマージュとどこで区別されるのかと言えば、それは前者のほうが次のような必然性に服しているという点においてである。すなわち、自らが含むあらゆる点によって他のイマージュの全ての点にお作用を及ぼし、自分が受け取るものの全体を伝達し、受けた作用に反対向きの等価な価値を対立させ、かくして広大無辺な宇宙のうちに伝播していく変容があらゆる向きに通過していくその通路である以外にない、という必然性だ。こうしたイマージュを、それのみ孤立させ、とりわけその外皮だけを切り離すことができるなら、私はそれを表象に変換できるはずである。」
表象イマージュは、存在イマージュを満たしているものを一挙に削除して、ただその外皮を残すことによって生じる。存在のイマージュを満たしているものとは、分子や原子のようなイマージュがまず考えられるだろう。当然それは間違いではない。しかし、ここでベルクソンが存在のイマージュを満たしているものということによって示そうとしているのは、当の存在イマージュがイマージュの総体の中で関係している関係の総体のことである。そのため、原子や分子が他のイマージュと重力によってどれほど遠くのものと関係しえようと、その存在イマージュを満たす関係の一部でしかない。そして、こうした関係をほとんど一挙に削除して残る外皮とは、ある生物が欲求し、その欲求に満足を与える自己の可能的行為に関係づけられた存在イマージュの一側面ということになる。ゆえに外皮とは、存在イマージュの単なる側面ではなく、その存在イマージュが関係しうる全関係の中で、知覚を行う生物が自らの欲求と可能的行為によって関係しうることのできる側面ということになる。イマージュにおいては、あることと意識的に知覚されることの間にあるのは、単なる程度の差ということになる。つまり権利上はあることと知覚することは同一でありうる。これは、意識的知覚が、「もの」とは別の場所にあるとされる意識なるものの内部で、「表象」を生むことによって成り立っていることを否定している。
「知覚は感覚中枢にも存在していない。知覚は、それらの中枢の関係の複雑性を示す尺度となりつつ、知覚が現れているその場所に存在するのだ。」
つまり知覚は、身体を中心とした知覚対象を含むそれら全体の中にあって、知覚対象をそれがあるがままの場所に表象化しつつ、まさにそこに生じる。それがあるがままに表象化されるかどうかについては、その身体をもつ生物の非決定性を尺度としている。しかし、あるがままに知覚できないと言っても、それは現に知覚与えられているものよりも、知覚対象である物質がより多くのをもので満たされており、その全てと知覚が関係することができないという意味であり、知覚があるがままに知覚することのできない別物があるということではない。さらに論をすすめるならば、身体というイマージュが、知覚より先に存在しているという考えも否定されることになるであろう。
「私の身体とは、これらの知覚の中心に浮かび上がってくるものであり、私という個人的人格とは、これらの行為を帰されるべき存在のことである。」
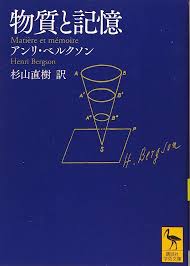

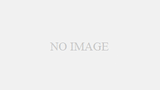
コメント