二十世紀の医療の歴史には、二つの分水嶺がある。最初の分水嶺は、二十世紀初頭の科学的発見の数々がもたらした医療技術の進歩である。
水の浄化→下痢等による幼児の死亡率の低下
アスピリンの使用→リウマチの痛みの緩和
キニーネの使用→マラリアの回復
ネズミ駆除→ペスト感染の予防
インシュリン→糖尿病患者の延命
栄養のある食事やきれいな水や空気、身体の清潔さ等が健康と関連することが科学的に認められたのもこの時期であり、それが公衆衛生として一般に広がった。こうした公衆衛生の技術を含む道具は、技術者による開発を前提としたが、医者等の専門家を介さずに、各人がそれほど高額でない費用で使用することができた。二十世紀医療の最初の分水嶺とは、つまり科学的に進歩した医療道具が、誰にでも仕えられ、誰もがその道具の主人となりえたことを意味するだろう。
しかし、まもなく第二の分水嶺が起こった。それは医療道具の開発や使用を、資格を有する専門家に集中させたことによる。それによって、医療は制度化され、大病院といった施設も多く設立されていった。こうして、個人がわずかな費用で使用できた諸道具は専門家に独占されていった。これらの道具を独占するのは資格を持つ専門家だけではない。国家もまた彼らに資格を与えることによって、その分前を得るようになった。医療の権威というのは、これらの道具を個人から収奪することによって、全社会構成員を医療制度(医療の専門化、大規模集中化)に依存させた結果によるものだ。道具が専門家に独占されるようになると、その道具を使用するための費用を専門家に支払わなくてはならない。それによって、人々は道具から経済的に遠ざけられ、また、専門家にしか扱えないという思考が常識化することによって心理的にも遠ざけられた。このように二重の仕方で遠ざけられた医療道具はいっそう価値あるものだと思われ、それに依存する状態が生まれたのである。
医療制度と大規模施設を介して、医療行為は抜け目なく世間に広がったといえるかもしれない。しかし、その効果を管理し、産業的に活用しようとする新たな規範権力を医療行為の普及と同じくして抜け目なく世間に行き渡らせることを可能にした。それは、公衆衛生が個人にもたらした健康の増進、つまり個人が最初の分水嶺において道具の主人となって得ることができた健康という美徳を、労働の条件という産業的に好ましいものへと変えることだった。つまり健康であるだけでは美徳とは言えなくなったのである。何のために役にたつ健康か?その答えは簡単である。勤労するための健康である。そしてこの意味における健康だけが美徳とされるに至ったのである。健康の条件としての労働というものはそれまで存在しなかったはずである。ゆえに、方法と目的が逆転したとは言えない。しかし、健康と労働という、関係をもたなかったもの同士の間に緊張関係が誕生したのは、この第二の分水嶺によるといえるだろう。
「皮肉なことに、手段が簡単になればなるほど、医師という専門職がますますその手段の独占を主張するようになり、医療従事者が最も簡単な手段さえ合法的に使用することを許されるまでの訓練期間がますます長くなり、全社会構成員がますます医師に依存するようになった。健康維持は美徳から一転して、科学の祭壇で行われる儀式に変わった。」
医療制度を介した道具の大量かつ集中的な使用は、X線の遺伝子損傷、薬剤耐性を持つ新たなウイルスの誕生、そして広い意味での環境汚染を生むに至った。医療道具の価値は、最初の分水嶺のときには原材料費と生産にかかる人件費と流通にかかる交通費だけだったものが、第二の分水嶺を越えると、医者を含めた医療制度を再生産するための費用、さらには人体や自然環境に対する人工的な汚染の食い止め、あるいはそれらを再治療、隠蔽するための費用までもが、医療道具の価値に上積みされていったのである。
「第二の分水嶺の頃には、不健康な環境に住み、医療に依存する人々の病んだ生命を保護することが、医療専門家の主要な仕事となった。」
「少数の患者は色々な臓器の移植によって、より長く生きのびることができた。他方、医療によって強要される社会全体の費用は、ありきたりの用語では計れないものになった。社会は、診療によって生じた幻覚、社会管理、引きのばされた苦痛、孤独、遺伝子的劣化、欲求不満といった否定的価値を総計するためのいかなる量的基準ももっていない。(…)それまでの達成によって立証された進歩が、価値のサービスという形をとった社会まるごとの搾取に対する論理的根拠として用いられる。その価値は、社会の単なる一構成分子、つまり自分で自分を有資格化する専門職エリートのひとつによって決定されたえず改訂されるのだ。」
「成長熱にうかされた社会では、まさにより多くのものを投入することが価値あることのように見えるのである。爆弾をもっと、警察をもっと、医学検査をもっと、教師をもっとというだけではなく、情報をもっと、研究をもっとという絶望的な懇願の声があげられる。」
少し話はずれるが、原子爆弾をもつことによって、つまり国家そのものを破壊することが可能になってはじめて全国家構成員に対する憎悪が生まれたのではなかろうか?そうとは言えなくとも、ある国家に属する誰かへの憎悪が増大していく過程には、全滅させうる可能性が背後に影のようにあるように思われる。ゴキブリは、一匹ずつを叩き潰していたとき、さらには一匹づつ殺虫剤で殺していた頃までは、今のようなゴキブリに対する人々の恐れは少なかったような気がする。自分の手を汚さず巣ごと壊滅させる殺虫薬が流通して初めて、大勢のうちの一匹としてゴキブリは私たちの前に現れ始めたのではなかろうか?そして大勢を想像させるその一匹に憎しみと恐怖が備わっているのではなかろうか?道具が他者との直接的な結びつきを媒介することもあれば、またはある集団の中の一人として憎悪を生み出すことにもなるのだ。
「科学と技術が問題を生み出した場合、それを克服しうるのはより多くの科学的知識とよりよい技術しかない、というのが今日流行の言い草になっている。悪しき管理の是正策は、管理の増強なのだ。」
また話は逸れるが、マイナンバーカードの普及に伴う数多の問題は、より強力な管理を生む理論的根拠とされるのだから、それ自体は決して廃止にはならない。しかし、生と死が管理されることによる影響は私たちの生き方そのものに影響を与えるだろう。それによって仮想的身体と呼ばれるものが、生身の身体を代替し、50歳までにすべきこと、60歳までにすべきこと、死ぬまでにすべきこと、人生100年時代、終活といった言説の数々を、血や肉の代わりに体内に宿し、あらゆる臓器と交流し、さらなる広告や医療行為を喜んで迎え入れるようなそんな身体を私たちは生きるべきではない。
第二の分水嶺が越えられた頃、第一の分水嶺の頃までは当然のこととして何千年も続いてきた当たり前の人間の姿が一瞬にして消えたのだ。それは、死の床で付きっきりで病人の看病にあたる家族や親戚たちの光景である。死に臨む人の前から、多くの世話人を排除し、老人ホーム、大病院、葬儀者といったサービスがそれを奪った。
祖父が脳梗塞で倒れたとき、祖父は椅子にもたれ掛かり、天井の何処かを見つめ、大きな目をぐるぐると回しながら、「早よ、(救急車を)呼べ」と母と祖母に叫んでいた。母と祖母は慌てながらも、案外冷静に、まずかかりつけの医師に電話して判断を仰いだ。そしてその後、救急車を呼んだ。私は母と祖母がはじめに救急車を呼ばないことに苛立ちを感じ、苦しむ祖父を横目に、居た堪れない気持ちでいた。私はすぐさまその場から逃げたかったのだ。そしてその通り私はその場から逃げ出した。そして私は救急車という救いの道具を求めて、玄関の門を飛び出したのだ。その行為を後に、救急車を呼びに行き、家まで案内したことを親戚に褒められたときには、小学生だった自分は、自分のことが恥ずかしく、横に座っている母を直視することができなかった。母は欺けないと思ったのだ。そのことが少年の心に一つの傷として残ったのは確かである。後の祖母の死にたいしても、このことが影響しているともいえる。祖母の死に対して私は何も語ることはできない。それは決して許されないこととして生きていかなければならない。語ることができないと語ることも、どこかで祖母に許し請うているのに違いないが。
祖父の死が、救急車、大病院、葬儀者という一連の道具によって片付けられたこと、そしてそれを憎悪しながらも、それらに救いを求めたこと。この事実をいかに受け止め、これから生きていけばよいのだろうか。
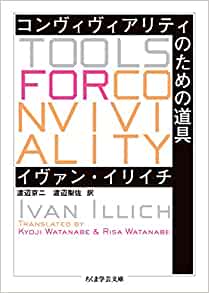


コメント