「現代の科学技術が管理する人にではなく、政治的に相互に結びついた個人に使えるような社会、それを私は“コンヴィヴィアル(=自立共生的)”と呼びたい。」
「ひとつのやりかたは、機能の専門化と制度化と権力の集中をもたらし、人々を官僚制と機械の付属物に変えてしまう。もうひとつのやりかたは、それぞれの人間の能力と管理と自発性の範囲を拡大する。そしてその範囲は、他の個人の同じ範囲での機能と自由の要求によってのみ制限されるのだ。」
科学技術、学校制度、個人利用されるAIなどの先端技術から手作業の工具にいたるまでの広い意味での「道具」をいかに使用するかによって、私たちはより高度に管理される産業主義的な成長を持続する社会を選ぶのか、または、道具によって管理されることを拒否し、脱産業主義的な自律共生的な社会を目指すのかという選択肢を提示している。管理されることを拒否するということは、専門家によって生産された道具(制度や施設、サービスを含む)への依存を減らすことによってのみ可能である。
「管理は、管理を必要ならしめる機構と、それゆえに管理に支配力を与える産出物への需要を除去することによってのみ、廃絶することができる」
私たちは、健康保険という制度への依存によって、マイナンバーという個人番号によって一括的に管理されることを許してしまった。預金口座や消費履歴、健康情報や職業能力さらには位置情報までもがリアルタイムでマイナンバーに紐づけられて管理される社会が現実してしまった。しかし、私たちは生きている限り、管理されることに抗って可能な限り自発性の範囲を拡げ、人格的な関係を道具と結ぶことができるはずである。そして、それを通じて他者とも自立的共生的な関係を築けるはずである。そのための足掛かりとして、わかりやすいのが電気やガスといったエネルギーへの依存を減らすことや、スマートフォンが提供しうる人格的結びつきを超える過剰なサービスへの依存を減らすことなどが挙げられる。しかし、こうした身近なものへの依存からの脱却は果てしなく遠い最終到着点でもある。なぜならば、依存からの脱却が安易な節約によるものだとすれば、それは欲求不満と不健康を生みだす結果にしかならないからである。依存には、量の依存(大量消費)、質への依存(激安スーパー、コスパ重視)、速度への依存(流行の移り変わりによって、依存先を転々とする)など、考慮するべきことがたくさんあるだろうが、ここでは詳述を避ける。
人は、自分が主人となって使用する道具によってのみ自分を社会のなかに意味づけることができる。また逆に自分が道具(国家、学校、会社、サービス、工場機械なども含む)に使われ、つまり道具への依存が大きければ大きいほど、支配される度合いも大きくなり、道具によって自己イメージを決定されるようになる。このようにして決定された自己イメージは自信喪失や移ろいやすい社会の中における自分の無意味さを感じることへとつながる。その結果として、自分が主人となりうる別の道具の消費へと駆り立てることにもなりかねない。そうした消費によって自己イメージを塗り替え、塗り替えた自己イメージを再び社会の中に投影、つまり意味づけようとするだろう。しかしSNSのような道具に頼るならば、消費に消費を重ねることになる。つまりトレンドや新商品の消費とそれを社会に発信するSNSのような道具の消費である。こうした消費は道具の依存を強めあい、いっそう過剰かつ同質的な消費へと人々を導く。矛盾するようだが、こうした道具の使用の中で自己を社会に意味づけるには、カリスマと認められ、商品とそれを紹介する道具の繋がりの中から自己を切り離さなくてはならないのだ。つまり自己が他者に消費される道具のひとつではなくなり、他者の評価に無関心でいられるときに限られるのである。このような消費から抜け出す別の道は存在しないのだろうか?節約がこのような無際限な消費を断ち切ろうとする試みであることは確かである。しかし節約によって自分を直接社会に意味づけることはできない。節約とは所詮消極的な消費に過ぎないからである。節約法を共有する方法はもちろん考えられる。そしてそれは一定の効果を生むだろう。しかしそれによって人々は相対的な貧困へと向かう。それは富める者との比較を打ち切ることができないからである。
そこで助けとなるのが、イリイチの「コンヴィヴィアリティ」という概念の活用である。
コンヴィヴィアリティのための道具の使用は、単なる道具の消費ではない。また当然ながら道具の消費による自己の商品化でもない。本書のタイトルにもなっている「コンヴィヴィアル」という語は、スペイン語の「エウトラぺリア(=節制ある楽しみ)」に由来している。「コンヴィヴィアルのための道具」つまり「節制ある楽しみのための道具」は、道具が人間と人格的な結びつきを失った場合、節度を保った人生の楽しみを破壊してしまうことになると警告しているのである。
コンヴィヴィアルとは、第一に、自分のための道具の使用、それによってなされる自分のための生産を意味している(この理解にはまだ確信がもてない)。そしてまた自分のつくりだしたものから生産や消費の限界を学ぶ過程を意味する。この限界と節制を知ることこそが、自ずと他者の自発性を侵害しないことへとつながる。それゆえに、自立のための生産でありながら同時に共生的な生産でもあるのである。この過程は、年齢を重ねるごとに習熟へと向かい、老いや死によって限界づけられる。身近なものへの依存から身を引き離すことが、いかに多くの道具との関りを必要とし、またいかに多くのことを学ばなくてはならないかをこの過程は教えてくれる。しかし、この過程を経なければ、管理と管理に支配力を与える生産物への需要から脱却することはできないだろう。
教育がもたらす専門化の育成とそうした専門家への道具の集中が、こうした依存の循環を体制化してしまっているのだから、私たちはまず学習を自分たちの手の中に取り戻さなくてはならない。そして、教育が隔てた学習と実践の距離を埋め、作りながら学ぶこと、学びながら作ることへの過程に、身を投じる勇気を持たなくてはいけない。
「人々は自分が教えこまれたことは知っているが、自分のすることからはほとんど何も学ばない。人々は自分たちには“教育”が必要なのだと感じるようになる。」
かつては当然のこととしてあった「自分がしたことから学ぶ」というプロセスは、教育のようにその先に成果が結果として待っているようなものではない。「自分がしたことから学ぶ」というプロセス自体が結果なのであり、現代のような社会では成果となり得るのだ。そして、この成果は肉体に刻まれ、母語のように、いかなるものからの収奪にも最後まで抵抗するはずである。そして、あらゆるものへ通じうる逃げ道となるのである。
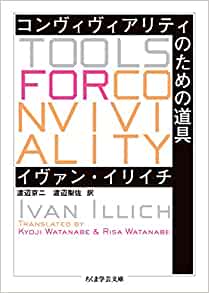
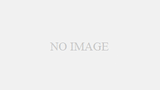

コメント