刑事精神鑑定書は三つの属性の言説によって成り立っている。
一つ目の言説は、一人の人間の自由を拘禁し、極端な場合は生と死までも決定する。警察による違法行為の証拠や証言の報告、裁判官や陪審員による有罪判決などがある。こうした言説が権力を持ちうるのは司法制度に由来する。当然ながら、精神鑑定医は自らの任務を超えて犯罪行為の有罪もしくは無罪の判決を下すことはできない。しかしながら、彼らは被疑者の刑事責任能力の有無を司法に対して報告する特権を与えられているため、精神鑑定書の中でこの属性の言説を用いることが可能となっている。
こうした言説を可能にするのは、司法制度に与えられた権力だけによるものではない。それが可能になるのは、警察の捜査報告や精神鑑定書などの中に見られる言説が、二つ目の属性である真理=科学的言説の価値を持っていることに由来する。真実を述べることを宣誓した警察官による科学的捜査(指紋捜査やDNA鑑定など)や医学的な精神鑑定の報告が真理=科学の言説という価値をもっていなければ、いかなる処罰も不可能である。
「真理の言説と司法の実践とのあいだに本質的な帰属関係が存在するというのは、司法、政治、批判にかかわる言説全体にとっての最も直接的で最も根源的な諸前提のうちの一つです」
フーコーは、精神鑑定書が上記の二つの言説によって成り立つことを「根源的な諸前提」と称しながら、しかし精神鑑定書には三つ目の言説が見てとられることを以下のように記述している。
「正義を決定するためにしつらえられた制度と真理を言表する資格を持った制度とが互いに出会うような地点、より手短に言うなら、法廷と学者とが出会うような地点、そのような地点において、真理の言説という価値をもち、裁判上の大きな効果を保持しているけれども、それにもかかわらず科学的言説形成の最も初歩的な規則とも無縁であるような、奇妙な属性を持った言葉が現れることがあります」
フーコーの言う奇妙な属性を持った言葉、これが三つ目の属性である、笑いを誘う言説である。笑いを誘う言説は、精神鑑定書の中で以下のように極端な表現で記されている箇所が見られる。
「Xは全くもって不道徳であり、反世間的であり、さらには口軽でもある」
「この男は、凡庸で、反体制である。記憶力はしっかりしており、筋道を立てて考えることもできる。道徳的な面について言えば、彼は反世間的であり、不道徳である。放蕩者であり、見るからに狡猾で、なかなか口を開こうとしない。」
「彼は極めて嫌悪すべき人間である」
「自分本来の姿より美しく見たてようとする」
「凡庸」「無能」「愚か」「軽薄」「愚鈍」「みすぼらしい」「貧相」「悪趣味」さらには「怠惰」「傲慢」「頑固」「悪意」といった日常的に親が子に用いるような言葉や子供の道徳教科書に見られる用語が笑いを誘う言説を構成している。
フーコーは、三つの言説の入り混じる精神鑑定書を「命を奪い笑いを誘う、日常的な真理の言説」と定義し、それを「グロテスク」と呼ぶ。フーコーは「グロテスク」という概念を以下のように示している。
「一つの言説あるいは個人が、その内在的な性質によっては許容されていないような権力の効果を、その地位ゆえに保持している」
日常的な道徳用語によって構成された笑いを誘う言説が、真理の価値を持ちながら、一人の人間の生と死を決定する効果を持ちうることを、フーコーはグロテスクと呼ぶ。ユダヤ人の大量虐殺を生んだガス室への移送が、歯車式に駆動する貧相で、無力な小役人たちからなる官僚制度によってなされたという事実もナチズムのグロテスクな権力を示している。森友事件において、事件に関与していたなら政治家の職を辞するという、安倍元首相の国会答弁もグロテスクな言表である。国会答弁は、その性質上、真理の言説の価値をもつ。しかしながら、安倍元首相の森友事件に関する答弁は低劣で、無数の虚偽を含んでいた。ゆえに国会という場における首相の価値を自ら進んではく奪するものであった。しかしながら、いやそれゆえに、その答弁に起源をもち、官僚制度を経由することによって権力の諸効果を伝搬し、首相の辞職を阻止するために一人の公務員の命を奪うまでに至ったのである。ここにグロテスクな権力をはっきりと見ることができる。
笑いを誘う言説が、なぜ精神鑑定書の内部で特権的な地位を得るようになったのか?本講義におけるフーコーの一大関心はここにある。
「そのような諸言説を利用しそれを機能させようとする権力のテクノロジーを見極めて、それを分析したいと考えています」
笑いを誘う言説が特権的な地位を得るようになった背景には、以下のような司法制度の慣習があった。
一つ目は、十八世紀末以来の刑法が、処罰しうるのは法律によってあらかじめ定義された違法行為のみであったことに由来する。裁かれるのは実行された違法行為そのものであり、それ以外にはないということである。このことは処罰権力が裁きうる対象が非常に限られていることを意味している。まだ実行されていない違法行為、将来の違法行為に対して処罰権力は何もできない。違法行為の先にあるまた別の違法行為、さらには違法行為を実行した犯罪者の存在様式は処罰権力の手の届かない余白として、実行された違法行為の傍でそれと重なるようにして存在していた。
二つ目は、有罪判決は、違法行為の事実が裁判官または陪審員が各々の内的確証へ至らなければ、下すことができないことに由来する。刑罰はオール・オア・ナッシングの法則に従い、証拠が不完全であるという心証が得られたならば罰することができないとされていた。しかしながら、証拠にわずかでも疑いがあることによって、無罪宣告が横行するのを防ぐ手だても必要とされた。その要求に答える形で司法制度に取り込まれたのが情状酌量である。情状酌量は、裁判官や陪審員の心的負担を低下させ、さらに当初の目的とは違った形で活用されるようになった。彼らが有罪性の心的確証を得られた度合いを、刑罰の大きさに反映できるようになったのである。情状酌量の司法的実践は、以下のような効果も保持していた。犯罪行為を直接実行した証拠が見つからない場合でも、無罪を下さなくてよくなったのである。昨今のママ友殺人に見受けられるように、共犯者=実行犯への洗脳=支配が認められたならば、被疑者は直接の犯罪行為者でなくても有罪となりうる。判決文に酌量の余地がないという言説をよく目にするが、それは酌量という制度がまずあって可能となる言説である。情状酌量という制度そのものは有罪を宣告しうる“違法なもの”の裾野を大きく広げる効果を持っていた。違法なものとは、法に定められた違法行為だけに止まらない。こうした司法の慣習が精神鑑定に特権的な権力を与えうる余白を産むことになったのである。
三つ目は、それまでの司法制度では、病気=犯罪が成り立たなかったことに由来する。犯罪行為の瞬間に精神疾患の症状が認められれば、刑事責任能力を持たないことが証明され、無罪が言い渡された。警察の捜査によって司法へ提出された犯罪の証拠が、被疑者の容疑を完全に証明していた場合でも、医学的=真理の言説が彼の刑事責任能力を否定したならば、無罪が宣告された。このような慣習を背景にして、「病気」と「犯罪」の間の余白を埋める必要を求められたのである。
こうした三つの背景が絡み合いながら、権力の余白を埋めるように、精神鑑定が台頭してきたのである。
精神鑑定が行うのは、当然のことながら被疑者の法的責任を決定することではない。そしてもはや、違法行為の瞬間における刑事責任能力を医学的=真理の言説によって根拠づけることでもない。精神鑑定が笑いを誘う言説によって行うのは、処罰権力を違法行為とは別のものへ適用させることである。
「精神鑑定は、違法行為から行動様式へ、犯罪から存在様式への移行を可能にし、そしてその存在様式を、まさしく犯罪そのものとして、ただし、いわば一人の個人行動様式のなかで一般性の状態にある犯罪そのものとして、出現させるのです。」
こうして「違反するもの」は、違法行為に限らなくなる。違法行為をなした、もしくはなしうる存在の存在様相もまた違反するものとなるのである。つまり正常な心理的発達を違反したものが処罰権力の適用対象となるのである。「したこと」から「あること」ないし「ある故に、しうること」へと処罰対象の位置がずらされたのである。こうして、処罰対象は道徳的性質に反しているものにまで拡大されるのである。被疑者は、犯罪者であると同時に非行者として責任を問われるのである。
「そこに現れたのは、世界に適応することができず、無秩序を愛し、常識はずれあるいは突飛な振る舞いをし、道徳を嫌悪し、法律を否認して、殺人を犯すに至りうるような、一人の人物であり、この人物が、司法装置に提供されることになったのです。したがって、つまるところ、有罪判決が下されるのは、問題の殺人における実際の共犯者に対してではありません。そうではなくて、世界に適応できず、無秩序を愛し、犯罪に至る行為を犯すような、そうした人物が、有罪とされるのです。」
このような司法実践を可能にしたのは、まさしく精神鑑定が、司法制度に残る「病気」=「無罪」という慣習に亀裂を入れたことによる。それも、医学的=真理の言説ではなく、笑いを誘う言説によって。違法行為と病気という、裁かれる者の内部で同時に成り立ち得ない領域の事象を、笑いを誘う言説によって埋め合わせたことによるのである。犯罪と病気の領域の隙間を、「愚鈍」「不成功」「劣等」「貧困」「醜悪」「未成熟」「幼児症」などの語で埋め合わせ、新たに法廷へと出現させたものこそ異常という領域である。精神鑑定が、病気に近いけれど道徳的欠陥であるがゆえに病気ではない異常者を司法権力の前に連れ出すことによって、犯罪者は犯罪行為によって裁かれるのと同時に、その異常な存在のゆえに非行者としても裁かれることとなる。つまりその異常性が可能性としてもつ社会に対する危険性が裁かれる処罰対象に加わるのである。精神鑑定の言説は、犯罪行為の瞬間ではなく、その行為の瞬間の存在の異常さが、それが形成され始めた幼少のころにまで遡って暴き立て、幼少のころから犯罪を行うまでの一人の人間における連続性をうちたてるのである。
「以後、刑事制裁と関りを持つのは、責任があると認められた法的主体ではありません。そうではなくて、治療を施したり社会復帰させたりするために、危険な人物を分別して制裁を与えるべき者を引き受けるという、そうした技術に相関的な一つの要素が、刑事制裁と関りを持つことになります。つまり、以後、非行者としての個人を引き受けるのは、そうした正常化=規範化の技術である、ということです」
フーコーは続く講義の中で、この正常化=規範化の権力の技術が、いかにして司法的ないし医学的権力を拠り所としつつ、社会全体さらには個人の身体の中にまで浸透していったかを明らかにすることになる。
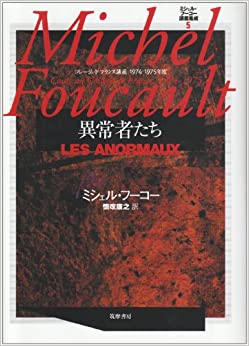
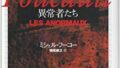
コメント